脳梗塞後遺症と新たな治療法
生活習慣病として有名な動脈硬化症(血管内にコレステロールが蓄積して硬く狭くなる病態)がどんどん悪くなると、脳の血管を塞いで脳梗塞を招きます。日本では脳梗塞の約3割が動脈硬化に関連しており、毎年4〜7万人が発症すると推計されています。脳梗塞になってしまうと、片麻痺(体の片側の麻痺)や構音障害(発音が不明瞭になる障害)などの後遺症に悩まされることが問題になります。
リハビリテーションは後遺症の改善に重要ですが、それだけでは十分な回復が得られない場合もあります。近年、自分の体から採取した脂肪由来幹細胞(ADSC)を培養で増やし、点滴で静脈に戻す再生医療が、新たな治療法として注目されています。このコラムでは、自己脂肪由来幹細胞の静脈投与による脳梗塞後遺症への効果とそのメカニズム、臨床研究のデータについて解説します。
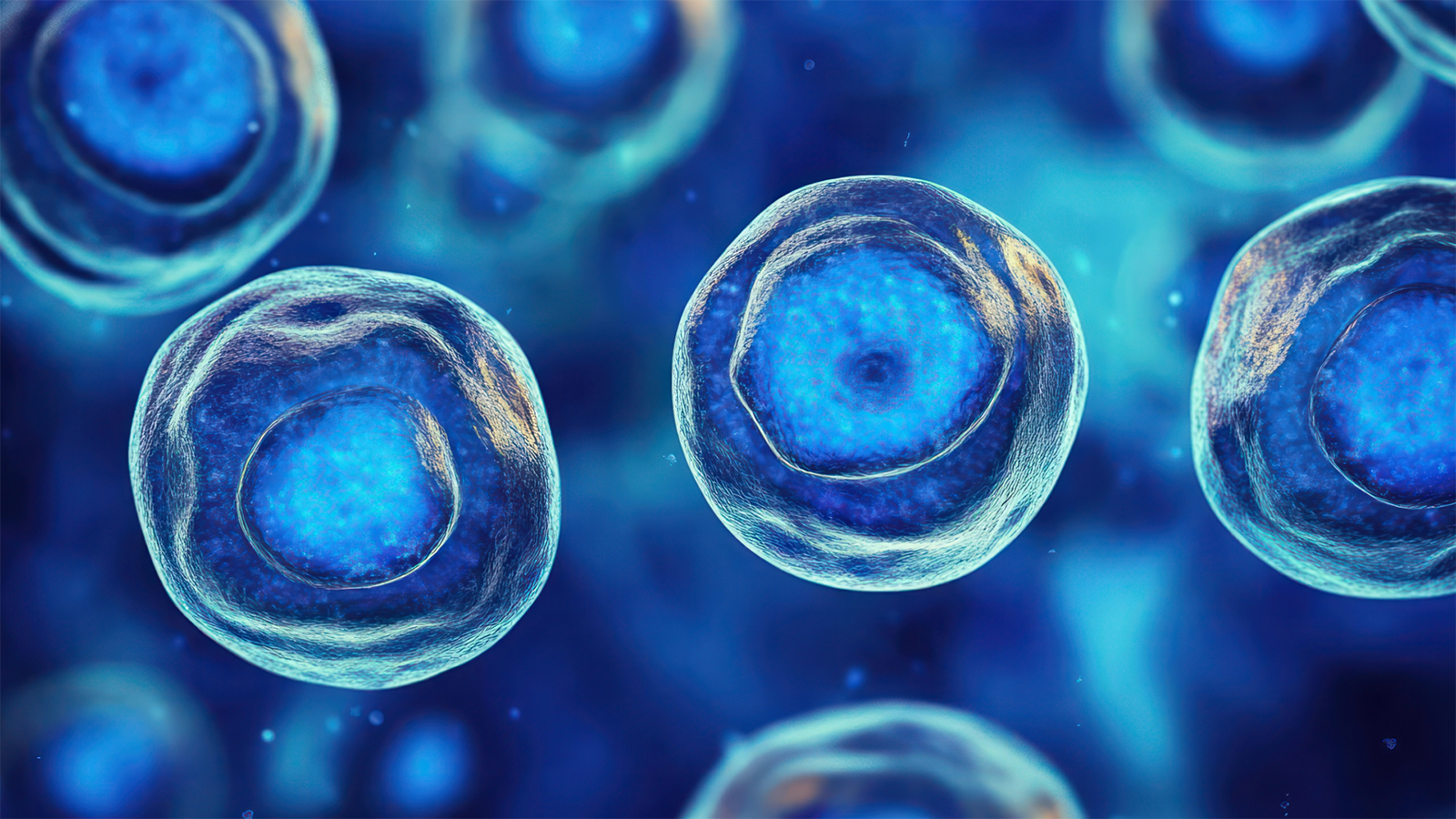
自己脂肪由来幹細胞(ADSC)療法とは?
脂肪由来幹細胞とは、皮下脂肪の中に存在する間葉系幹細胞の一種です。患者さん自身の腹部などから少量の脂肪組織を採取し、そこから幹細胞を分離して実験室で培養・増殖させます。十分な数(数千万~約2億個)の細胞に増やした上で、生理食塩水に懸濁して点滴静脈注射で体内に戻します。点滴は通常1~2時間かけて行われます。自分の細胞を用いるため拒絶反応の心配は少なく、安全性が高いと考えられています(後述)。培養した自己脂肪由来幹細胞を点滴投与するこの療法は、一部の医療機関で臨床研究や自由診療として実施されています。
期待される主な治療効果
自己脂肪由来幹細胞を静脈投与することで、脳梗塞によるさまざまな後遺症の改善が期待されています。実際の臨床研究から報告されている主な効果は以下の通りです。
- 運動機能の改善(麻痺の軽減): 脳梗塞後一番の問題になるのはやはり片麻痺(体の片側の麻痺)などの運動機能の障害になります。幹細胞治療はこの運動障害の改善に効果が期待できます。海外で行われた36名の慢性期脳梗塞患者を対象とした試験では、幹細胞点滴後6か月・12か月の時点で麻痺の重症度が統計的に有意に改善し、日常生活動作(ADL)が向上したことが確認されています。例えば、その研究ではBarthel指数(ADLの自立度を測る指数)の平均が治療前より12か月後に約10ポイント改善し、自立度の高い患者さんの割合が11.4%から35.5%に増加しました。
- 発話機能の改善: 構音障害などの発話の障害に対しても改善例があります。実際に、幹細胞点滴直後に声のかすれや発音の不明瞭さが改善したケースが報告されています。先述のケースでは、点滴により構音障害が軽減し、患者さんの声がはっきりしたといいます。このように話しづらさの軽減や飲み込みの改善など、言語聴覚領域への効果も期待されています。
- 感覚・認知機能の改善: 一部の患者さんでは、麻痺側の触覚や温度感覚の改善も観察されています。例えば、点滴後に麻痺していた手足の皮膚感覚が戻り、「温かさを感じる」と訴えた例があります。また、認知機能の向上を示唆する報告や、抑うつ状態の改善(うつ症状の軽減)も認められたとの報告があります。実際、前述の36人の試験では認知機能検査(MMSE)やうつ症状評価においても、治療6か月後と12か月後に有意な改善が見られています。
- 皮膚血流の改善: 幹細胞の投与によって麻痺した手足の血行が良くなることも指摘されています。点滴中に麻痺肢の皮膚温が上昇し、肘や膝が赤みを帯びたケースが報告されました。これは血流や代謝の改善を反映している可能性があります。
こうした効果は、脳梗塞からの経過時間に影響を受けることもわかってきました。発症から比較的早い時期(半年以内)に幹細胞治療を受けた方が、発症後1年以上経ってから受けた場合よりも改善が顕著だったとの報告があります。その一方で、患者さんの年齢や性別、脳梗塞のタイプ(脳梗塞か脳出血か)による効果の差は認められなかったとされています。現時点では個人差もありますが、幹細胞療法はリハビリだけでは得られにくい追加の回復をもたらす可能性が期待されています。
幹細胞治療が効く仕組み
「体に点滴した幹細胞がどのように効くのか?」という疑問はもっともです。実は、投与された幹細胞がそのまま脳内で新しい神経細胞に生まれ変わって置き換わるわけではないと考えられています。主な作用メカニズムは次の通りです。
- 損なわれた脳の“修復支援”: 幹細胞は損傷した脳の組織修復を間接的に助けます。幹細胞は体内で様々な有益な物質(サイトカインや成長因子、エクソソームなど)を放出し、これが脳の自己修復メカニズムを活性化すると考えられます。その結果、神経の再生や軸索の成長(傷ついた神経回路の再連結)が促進され、脳の健全な部分が障害を補う「脳の可塑性」が高まると期待されています。
- 炎症の抑制: 脳梗塞の後には、損傷部位に炎症反応が起こり、周囲の細胞に二次的なダメージを与えることがあります。幹細胞には抗炎症作用や免疫調節作用があり、過剰な炎症を和らげて脳を守る働きがあります。実際、幹細胞を投与すると炎症を誘導するサイトカイン(炎症性物質)が減少し、神経細胞の生存環境が改善することが動物実験などで示されています。
- 血管新生(新しい血管の再生): 幹細胞が出す物質の作用で新しい毛細血管の生成(血管新生)が促進され、血流が良くなる可能性があります。梗塞でダメージを受けた領域に新たな血管ネットワークが形成されれば、酸素や栄養の供給が改善し、組織の回復につながります。また、血管のリモデリング(再構築)も促されると考えられています。
- 脳組織の保護と再生: 幹細胞由来のエクソソームと呼ばれる微小な粒子(細胞外小胞)が重要な役割を果たしていることもわかってきました。エクソソームにはタンパク質やマイクロRNAなどの情報分子が含まれ、これが傷ついた神経細胞に取り込まれることで、細胞死を抑制したり代謝を正常化したりする効果があります。要するに、幹細胞が放出する「回復を促すメッセージ」が脳に伝わり、神経細胞や支持細胞が元気を取り戻す手助けをしていると考えられます。
このように幹細胞療法は、薬剤では実現できなかった多面的なアプローチ(炎症の制御、血管・神経の再生促進など)で脳の回復力を引き出す点が大きな特徴です。これらの作用は主に点滴後すぐから数日間にかけて幹細胞が分泌する物質によって生じる間接的な効果であり、点滴直後から効果が現れる背景にはこのパラクリン効果(傍分泌効果)があると考えられています。
臨床研究が示す有効性エビデンス
自己脂肪由来幹細胞静脈投与の効果と安全性について、世界中で様々な臨床研究が行われています。ここでは代表的な研究結果を紹介します。
- 日本における少数例研究(慢性期の患者21名): 日本の研究グループが、発症から4か月~8年経過した脳梗塞後遺症の患者21名に自己脂肪由来幹細胞を点滴投与し、経過を追っています。その結果、21例中16例で何らかの神経機能の改善が確認されました。特に発症から半年以内の比較的早期に治療を受けた患者ほど改善が顕著で、治療数時間以内にNIHSSの改善が見られた例も多数報告されています。一部の患者では治療直後の著明な改善効果がそのまま1か月後も持続しており、単回の点滴でも持続的な回復効果を得られる可能性が示唆されました。この研究では重大な副作用も認められず、自己脂肪幹細胞療法の有望性が示されています。
※NIHSS(NIH Stroke Scale):意識レベル、視野、運動麻痺、言語など項目ごとに評価し合計0~42点で重症度を判定するスケール(数値が大きいほど重症)。 - 海外Phase I/II試験(慢性期の患者36名): アメリカを中心とした研究では、脳梗塞発症後6か月以上経過しリハビリで改善が頭打ちになった慢性期患者36名を対象に、同種(他人由来)の脂肪幹細胞を単回静脈点滴する臨床試験が行われました。安全性を確認しつつ段階的に投与量を増やすデザインで、最終的には体重1kgあたり150万個(全体で約1.5億個程度)の細胞を点滴しています。その結果、重大な有害事象は投与群・プラセボ群間で差はなく(幹細胞による有害な作用は特に認められない)、安全に投与できることが確認されました。さらに、6か月後および12か月後の追跡で、幹細胞を受けた患者はプラセボ群に比べて運動機能・ADL・認知機能・気分のすべてで改善を示しました。特にADLの指標であるBarthel指数は治療群で有意に向上し、12か月後には約35%の患者がほぼ自立できるレベルに達しています。この研究は症例数が比較的大きく、信頼性の高いデータといえます。その結論として「慢性期脳卒中患者に対する静脈内幹細胞療法は安全で、機能面で有益な効果を示す」と報告されています。
- 過去の研究とメタアナリシス(総括的な解析): 世界初期の研究として、2011年日本の研究者が自家骨髄由来のMSC(間葉系幹細胞)を点滴投与したところ、12名の脳梗塞患者で安全性が確認され、NIHSSやmRS(改訂Rankinスケール)の改善が得られたと報告しました。その後もインドや韓国などで少人数の予備的臨床研究が行われ、いずれも深刻な副作用なくわずかながら機能回復につながるとの結果が報告されています。さらに近年では、世界中の臨床試験結果をまとめて効果を検証するメタアナリシスも行われました。その一つでは、合計740名の脳梗塞患者データ(RCT9件+非RCT7件)を解析し、幹細胞療法を受けた群は従来治療のみの群に比べて神経学的な障害が有意に軽減し、日常生活動作も向上していたことが示されています。死亡率や再発率に差はなく、安全性にも大きな問題は認められませんでした。もっとも、試験ごとの規模が小さいため統計的ばらつきは大きく、現時点では「効果は有望だがエビデンス蓄積はこれから」と総括されています。
以上のように、自己脂肪由来幹細胞静脈投与は国内外の臨床研究で概ね安全かつ有望な効果が示されています。ただし、依然として症例数は限られており、効果の程度には個人差もあります。より大規模なプラセボ対照試験や長期経過のデータ蓄積が今後の課題です。
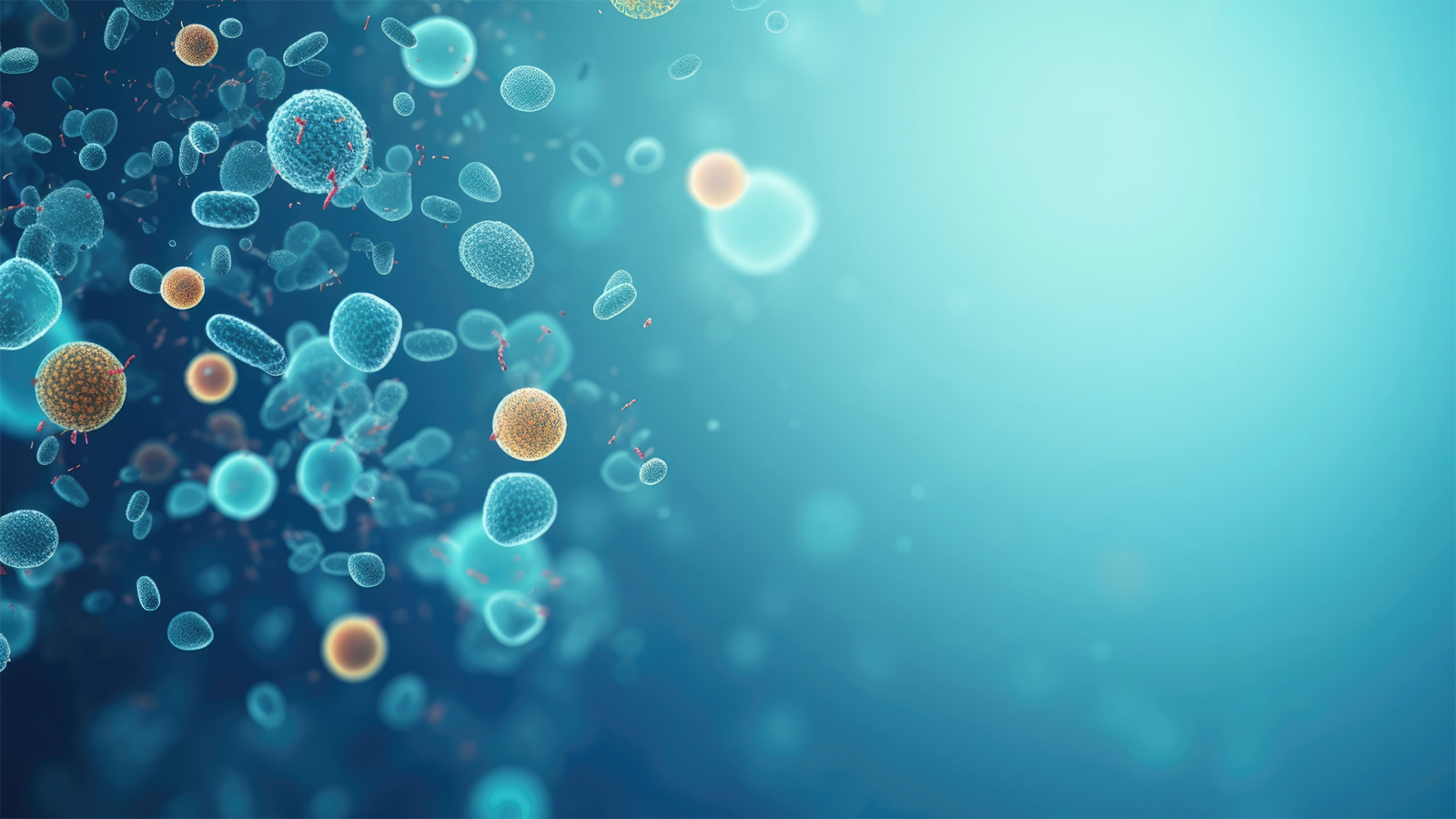
投与プロトコル・回数と効果の持続期間
投与プロトコル(方法): 患者さん自身の脂肪から幹細胞を取り出し培養するには約4~6週間かかります。培養して増やした幹細胞は、点滴によりゆっくり血管内へ戻します。臨床研究の多くは単回投与で設計されていますが、将来的には状態に応じて複数回投与することも検討されています(動物実験では週1回の点滴を3回行うことで効果が増強したとの報告もあります)。投与される細胞数は研究により様々ですが、だいたい数千万~数億個規模です。
効果の持続期間: 幹細胞療法による改善効果がどのくらい持続するかは、まだ十分に明らかではありません。現時点の報告では少なくとも投与後数か月~1年程度は効果が維持もしくは更に向上する例が多いようです。例えば、ある研究では6か月後より12か月後の方がADLがさらに改善していたことから、半年~1年かけて徐々に回復していくケースも考えられます。一方、投与直後に大きな改善が見られた患者さんでは、その効果が少なくとも数ヶ月持続したとの報告があります。ただし中には、幹細胞治療後も明らかな改善が得られなかったり、効果が一時的だったりする例もあります。効果が持続しやすい患者の特徴や、必要に応じた追加投与のタイミングなど、最適な治療戦略を判断するのが必要です。
安全性と副作用について
患者さんにとって治療効果と同じくらい気になるのが安全性でしょう。幸いなことに、これまで報告された臨床研究において自己脂肪由来幹細胞の点滴による深刻な有害事象はほとんど報告されていません。自分の細胞を使う自家移植では拒絶反応もなく、安全性はさらに高いと考えられます。具体的に報告されている副作用・合併症としては、以下のようなものがあります。
- 一過性の発熱や頭痛: 点滴後に軽い発熱や頭痛が見られることがありますが、いずれも一時的で自然に治まっています。これは点滴による体液量負荷や細胞に対する一時的な反応による可能性があります。
- 感染症のリスク: 脂肪採取の小手術や培養過程での感染リスクは極めて低いものの、完全にゼロとは言えません。ただし適切な無菌操作と管理のもとで、これまで治療に関連する重篤な感染症の報告はありません。
- 腫瘍形成の懸念: 幹細胞治療では「がん化しないか?」と心配されることがあります。しかし、間葉系幹細胞は遺伝子的に安定で腫瘍化しにくいことが知られており、実際に臨床試験でも投与後の腫瘍発生は認められていません。長期的にも重大な問題は生じていないとの報告があります。
以上から、自己脂肪由来幹細胞静脈投与は概ね安全に実施できる治療法といえます。ただし、新しい治療である以上、慎重な経過観察が必要です。治療後は定期的に診察を受け、体調の変化や気になる症状があればすぐ主治医に報告するようにしましょう。
まとめ
培養した自己脂肪由来幹細胞の静脈投与は、脳梗塞後遺症に対する新しい再生医療の選択肢として期待されています。運動麻痺や言語障害などの改善が報告されており、その効果は幹細胞が放出する物質によって脳の自己回復力を引き出すことにあります。リハビリテーションと組み合わせることで、「あきらめていた機能がまた使えるようになる」可能性を広げる治療と言えるでしょう。
安全性もこれまでのところ良好で、大きな副作用は確認されていません。ただし、現時点では研究段階の治療であり、誰にでも確実に効くと断言できるものではありません。効果には個人差があり、医学的にも解明途上の部分が残されています。しかし、国内外で積み重ねられている臨床データは着実に前向きな結果を示しており、「脳梗塞の後遺症はもう治らない」という常識を変えつつあります。今後、より大規模な臨床試験によって有効性が証明され、保険診療として広く提供される日が来ることが期待されます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 幹細胞治療は脳梗塞からどれくらい経過していても受けられますか?
A. 発症後数ヶ月~数年経過している慢性期でも効果が期待されますが、発症から比較的早期(半年以内)の方が改善効果がより顕著になる傾向があります。
Q2. 幹細胞療法を受ければリハビリは不要になりますか?
A. 幹細胞治療はリハビリと併用することで相乗効果が得られる可能性があります。治療後も継続的にリハビリを行うことが推奨されています。
Q3. 幹細胞治療を受けた後、効果はどれくらい持続しますか?
A. 治療後、数ヶ月から1年程度は改善効果が持続または徐々に向上する可能性があります。ただし、個人差がありますので医師とよく相談してください。
Q4. 高齢の患者でも幹細胞療法は受けられますか?
A. 年齢による明確な制限はありません。高齢の方でも安全に治療を受けて効果が得られた報告がありますが、全身状態や合併症などを考慮し判断します。
Q5. 幹細胞を点滴すると、すぐに症状が改善しますか?
A. 点滴後に比較的早期(数時間~数日以内)に改善を感じるケースがありますが、一般的には数週間から数ヶ月かけて徐々に改善効果を実感する方が多いです。
Q6. 幹細胞治療を受ける場合、入院は必要ですか?
A. 通常、幹細胞点滴は外来で行われます。治療後に経過観察を行い、問題がなければ帰宅できます。
Q7. 幹細胞療法を何回か繰り返すことで効果はさらに高まりますか?
A. 一部の研究では複数回の投与でより良い結果が得られた報告もあり、症状や改善状況に応じて追加投与を検討することがあります。
Q8. 幹細胞療法はすべての後遺症に効くのでしょうか?
A. 運動麻痺や構音障害、感覚障害の改善例がありますが、効果には個人差があり、すべての後遺症に必ずしも同様の効果が得られるわけではありません。
Q9. 他の薬物療法と併用することは可能ですか?
A. 基本的に他の薬物療法との併用は可能です。ただし、免疫抑制剤など一部の薬剤との相互作用に関しては医師の指導が必要です。
Q10. 治療を受ける前にどんな検査や準備が必要ですか?
A. 幹細胞治療前には全身の健康状態を評価するための血液検査や画像検査が行われます。また、脂肪採取に伴う局所麻酔の可否なども事前に評価されます。
参考文献(Vancouverスタイル)
1. Ichihashi M, Tanaka M, Iizuka T, Nagoe N, Sato Y, et al. Therapeutic Effect of Intravenously Administered Autologous Adipocyte-Derived Stem Cells on Chronic Stage Stroke Patients. Int J Stem Cell Res Ther. 2020;7:070.
2. Levy ML, Crawford JR, Dib N, Verkh L, Tankovich N, Cramer SC. Phase I/II Study of Safety and Preliminary Efficacy of Intravenous Allogeneic Mesenchymal Stem Cells in Chronic Stroke. Stroke. 2019;50(10):2835-2841.
3. Li Z, Dong X, Tian M, Liu C, Wang K, Li L, Liu J. Stem cell-based therapies for ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Stem Cell Res Ther. 2020;11:252.
4. Honmou O, Houkin K, Matsunaga T, Niitsu Y, Ishiai S, et al. Intravenous administration of autologous mesenchymal stem cells expanded in autologous serum for stroke. Brain. 2011;134(Pt6):1790-1807.







とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)




