突然の事故や怪我で脊椎を損傷した場合、重い後遺症が残る可能性があります。近年、その治療法の新たな可能性として再生医療、特に幹細胞治療が注目されています。
今回は、脊椎損傷に対する従来の治療法から最新の再生医療まで、詳しく解説していきます。
◇脊椎損傷とは?
脊椎損傷の原因と分類
脊椎損傷とは、背骨(脊椎)の骨折や脱臼、圧迫により、内部を通る脊髄神経が傷つくことを言います。主な原因としては以下が挙げられます。
- 交通事故や転落事故などの外傷
- ラグビー、スキー、体操など激しいスポーツ
- 高齢者の転倒など日常生活での事故
脊椎損傷は、「完全損傷」と「不完全損傷」に分類されます。
完全損傷:脊髄が完全に断裂した状態で、損傷部位以下の運動機能や感覚が完全に失われます。
不完全損傷:脊髄が部分的に損傷しており、運動や感覚が一部残っています。
損傷レベルと症状の違い
脊椎損傷の症状は、損傷が起きた位置(レベル)によって異なります。一般的に、損傷箇所が首に近いほど広範囲の麻痺が生じます。
頸髄損傷:首の脊髄損傷で四肢麻痺や呼吸障害が生じることもあります。
胸髄損傷:胸のレベルでの損傷で、主に下半身に麻痺や感覚障害が現れます。
腰髄損傷:腰部での損傷により、下半身の運動や排泄機能に影響が出ることがあります。
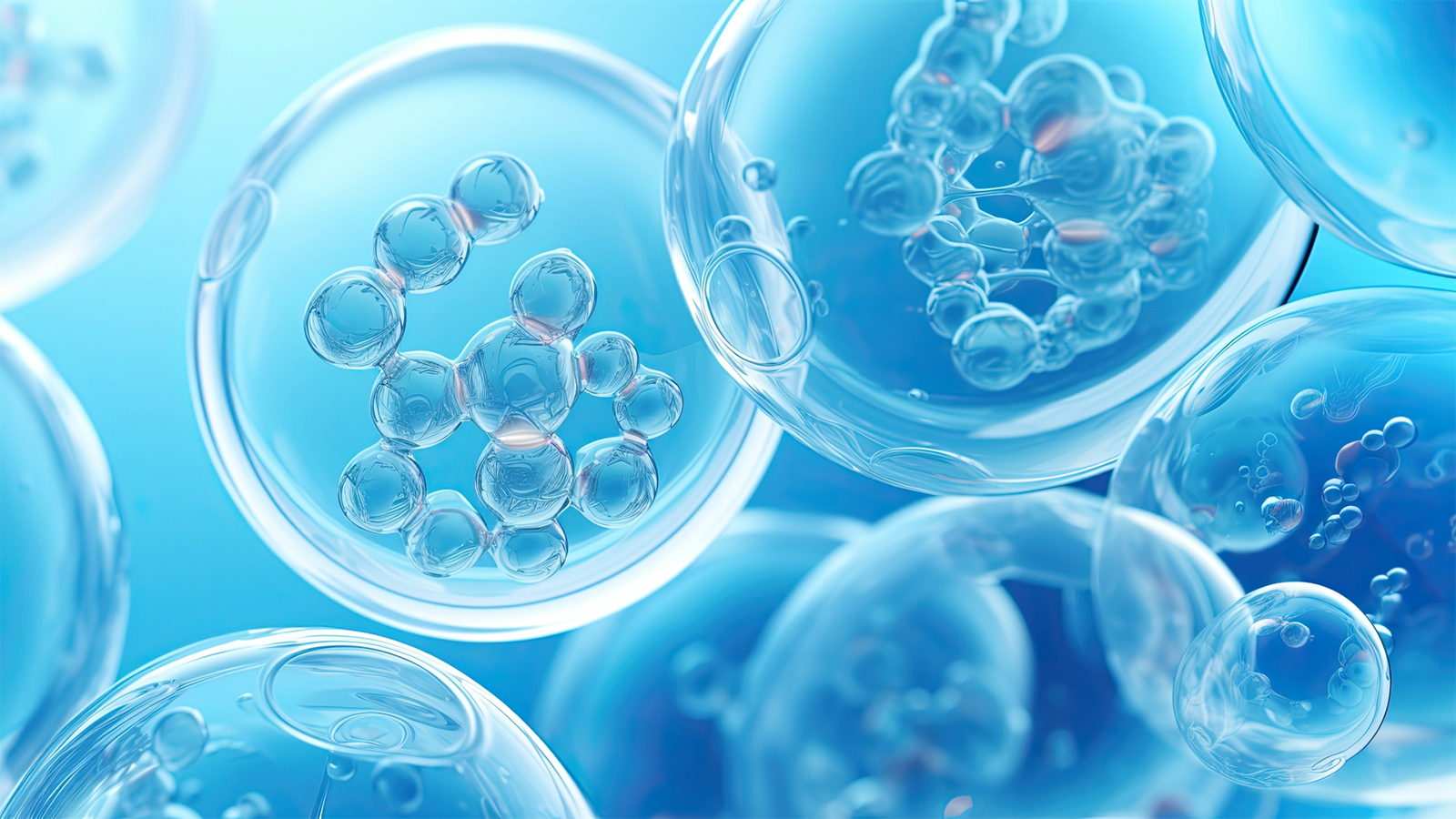
◇脊椎損傷が引き起こす後遺症と生活への影響
運動麻痺、感覚障害などの主な後遺症
脊椎損傷後には、以下のような後遺症が生じることがあります。
- 運動機能の麻痺(手足が動かなくなる)
- 感覚障害(触覚、温度感覚の消失)
- 排尿・排便障害(失禁や排尿困難)
- 褥瘡(床ずれ)のリスク増加
- 慢性的な痛み(神経痛や筋肉痛)
これらの症状により、日常生活の自立が困難になるケースが多く見られます。
日常生活や社会復帰への課題
脊椎損傷の後遺症は、身体的な問題だけでなく、心理的、社会的にも大きな影響を与えます。長期間にわたり介護やリハビリが必要になるため、本人や家族の負担が大きく、社会復帰が難しいケースもあります。
そのため、早期の治療とともに、効果的なリハビリや支援体制の整備が重要とされています。
◇脊椎損傷に対する従来の治療法
保存療法(リハビリ、薬物療法)の内容と限界
従来の脊椎損傷に対する治療法として、以下のような保存療法があります。
リハビリテーション(理学療法・作業療法)
- 麻痺した筋肉の維持、機能改善
- 日常生活動作の再獲得訓練
- 関節拘縮予防のためのストレッチ
薬物療法
- 鎮痛薬による痛みの管理
- 抗けいれん薬などによる神経障害性疼痛の緩和
しかし、これらの保存療法では脊髄神経の損傷そのものを修復することはできず、あくまで残存機能を維持し、改善を目指すに留まっています。
外科的治療(手術)の目的と課題
外科的治療(手術)は、脊椎の不安定性や圧迫を取り除くことを主な目的として行われます。主な手術法としては以下が挙げられます。
脊椎固定術
不安定な脊椎を金属製の器具で固定し、安定性を取り戻すことを目的としています。
減圧術(除圧術)
骨片や椎間板による脊髄への圧迫を取り除き、神経機能のさらなる悪化を防ぎます。
手術の目的は、脊髄へのさらなる損傷を防ぐことで、残存している神経機能を維持・改善することです。しかし、すでに損傷した神経を修復・再生することは難しく、完全な回復を期待することは困難です。
また、外科手術には以下の課題もあります。
- 感染症や出血、合併症などのリスク
- 手術後の長期的なリハビリや入院期間が必要
- 神経損傷そのものの修復には限界がある
これらの課題から、手術以外の新しい治療法への期待が高まっており、再生医療(幹細胞治療)が新たな可能性として注目されています。
◇ 注目される再生医療(幹細胞治療)とは?
再生医療(幹細胞治療)の基礎知識と仕組み
再生医療とは、損傷した組織や臓器を再生・修復し、その機能を回復させることを目的とする治療です。特に幹細胞を使った治療は、自ら増殖しさまざまな種類の細胞に分化できる幹細胞の能力を活用して、失われた組織を再構築する治療法です。
脊椎損傷に対する幹細胞治療では、患者自身または他者から採取した幹細胞を培養し、損傷した脊髄部分に移植します。この治療によって神経細胞の再生や修復が促され、損傷によって失われた機能を改善させることが期待されています。
脊髄神経損傷への幹細胞の作用メカニズム
幹細胞が脊髄神経損傷部位に作用するメカニズムとして、以下のような効果が考えられています。
神経細胞の直接的な再生促進
移植した幹細胞が神経細胞やその支持細胞に分化し、新たな神経回路の形成や既存神経の修復を促進します。
抗炎症作用と組織修復因子の放出
幹細胞が炎症を抑える物質や成長因子を分泌することで、損傷した脊髄の炎症を鎮め、自然な治癒過程を促します。
神経保護効果
損傷部位周囲の神経細胞がさらなる障害を受けることを防ぎ、神経機能の悪化を最小限に抑えることも期待されています。
これらのメカニズムにより、損傷した脊髄の回復が促進される可能性があります。

◇ 幹細胞治療が脊椎損傷にもたらす可能性
神経再生・修復による運動・感覚機能の改善
幹細胞治療が期待される最大のポイントは、従来の治療法では困難であった脊髄神経の再生・修復による機能回復の可能性です。脊椎損傷によって麻痺した手足の運動機能や、失われた感覚機能を改善できる可能性があり、日常生活の質(QOL)の向上につながることが期待されています。
幹細胞治療による機能改善の可能性が報告される臨床研究も出始めており、これまで回復が難しかった重度の症例にも新たな治療の希望をもたらしています。
従来の治療法との具体的な違い
従来の脊椎損傷の治療は、脊髄への圧迫除去や安定化を目的とした手術や、症状を和らげるための薬物療法、リハビリテーションによる残存機能の維持が中心でした。しかし、損傷した脊髄そのものを回復させることは困難でした。
一方、幹細胞治療は損傷した脊髄神経を再生・修復する可能性を追求する、根本的な治療法として期待されています。これまで不可能であった脊髄神経の機能回復という観点で、従来の治療とは根本的に異なります。
◇ 幹細胞治療が注目される背景と現状
医療技術の進展と臨床研究の進捗状況
再生医療技術は近年飛躍的に進歩し、特に幹細胞の培養・増殖技術や移植技術が大きく進展しました。これに伴い、世界中で脊髄損傷への臨床研究が活発に行われています。日本でも条件付き承認制度を活用し、幹細胞を用いた脊髄損傷治療の臨床研究が進められ、早期の実用化を目指す動きが加速しています。
世界的な幹細胞治療研究の現状
海外でも脊髄損傷に対する幹細胞治療の臨床試験が多数進行中です。特に米国や欧州では間葉系幹細胞、iPS細胞由来神経幹細胞などを用いた研究が進んでおり、複数の臨床試験で運動機能の改善など有望な結果が報告されています。ただし、安全性や治療効果の長期的評価については、さらに慎重な検証が必要とされています。
◇ 幹細胞治療の課題と今後の展望
安全性と有効性に関する今後の課題
幹細胞治療が本格的に普及するためには、細胞移植後の安全性の確保(腫瘍化リスクや拒絶反応の管理)と、治療効果の長期的な検証が重要です。また、治療の標準化と安定した再現性を確保することも課題です。
今後さらに多くの臨床データを蓄積し、治療適応の範囲や最適な治療方法が明確にされることで、広く実用化される可能性が高まるでしょう。
日本における治療承認の現状と見通し
日本では、札幌医科大学とニプロが共同開発した脊髄損傷に対する幹細胞治療製品「ステミラック注」が2018年に条件付き承認され、現在臨床データが収集されています。この取り組みが成功すれば、2025年以降の正式承認へとつながる見通しです。
また、iPS細胞を用いた臨床研究も進んでおり、さらなる治療選択肢が増える可能性もあります。日本における再生医療の承認環境は今後も拡充されていくと考えられます。
◇よくある質問(Q&A)
Q1. 脊椎損傷と脊髄損傷の違いは何ですか?
A. 脊椎損傷は背骨そのものの骨折や脱臼を指し、脊髄損傷は背骨の中を通る神経(脊髄)が傷つくことを指します。脊椎損傷が必ずしも脊髄損傷を伴うわけではありませんが、多くの場合、脊椎損傷が原因で脊髄損傷が起こります。
Q2. 脊椎損傷で障害を負った後、日常生活で特に注意すべき点は何ですか?
A. 特に褥瘡(床ずれ)や排泄障害による尿路感染症、筋肉や関節の拘縮などの二次障害の予防が重要です。定期的な体位変換や適切なリハビリ、衛生管理が欠かせません。
Q3. 脊椎損傷の後遺症で生じる麻痺はどの程度回復しますか?
A. 損傷の程度によりますが、特に不完全損傷の場合は早期からのリハビリによって部分的な回復が期待できます。完全損傷の場合でも、残存機能を最大限活用するためのリハビリが推奨されています。
Q4. 脊椎損傷に伴う痛みはどのような痛みですか?
A. 主に神経障害性疼痛と筋骨格系の痛みがあります。神経障害性疼痛は刺すような鋭い痛みやしびれを伴い、筋骨格系の痛みは筋肉や関節のこわばりなどが特徴です。
Q5. 脊椎損傷による麻痺のリハビリはどのくらいの期間が必要ですか?
A. 一般的には受傷後6ヶ月から2年ほどが集中的なリハビリ期間ですが、その後も機能維持のために長期的にリハビリを継続することが望ましいです。
Q6. 脊椎損傷は高齢者と若年者では治療やリハビリの内容が異なりますか?
A. 基本的な治療方針は共通していますが、高齢者では骨粗鬆症や合併症の管理を重点的に行い、若年者では職場復帰やスポーツ復帰など、社会復帰を視野に入れたリハビリを重視する傾向があります。
Q7. 脊椎損傷が疑われる場合、どのような検査が行われますか?
A. まずはレントゲン検査を行い、必要に応じてMRIやCT検査で脊髄や骨の状態を詳しく確認します。これらの画像診断により損傷の位置や程度が正確に把握されます。
Q8. 脊椎損傷で車椅子生活になった場合、どのような住宅環境の整備が必要でしょうか?
A. 段差の解消やスロープの設置、広い廊下やドア、トイレや浴室のバリアフリー化などが重要です。また、車椅子対応のキッチンや家具配置などの工夫も生活の質を高めるために有効です。
◇まとめ
脊椎損傷に対する幹細胞治療は、従来の治療法では回復が難しかった神経機能の修復に新たな可能性をもたらしています。しかしながら、現時点では治療効果の明確な証明や安全性の確認にまだ課題が残っています。日本国内でも先進的な研究が進行中であり、今後の治療承認の拡大や一般臨床への普及に注目が集まっています。
脊椎損傷という困難な病態に対して、幹細胞治療が真に希望となるかどうかは、さらなる研究成果と臨床データの蓄積にかかっています。この記事が、治療を考える上での客観的な情報提供としてお役に立てれば幸いです。





とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)






