足の動脈硬化と血流障害のしくみ<無症状でも注意!>
動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールなどのプラークが蓄積して血管が狭く硬くなる状態です。この動脈硬化が脚の動脈で進行すると、足先への血流が不足してしまう病気を下肢閉塞性動脈硬化症(Peripheral Arterial Disease, PAD)と呼びます。
初期には症状が出にくく、実際PAD患者の約半数は自覚症状がありません。そのため見逃されがちですが、無症状でも動脈硬化は進行しうるので注意が必要です。中等症(中程度のPAD)になると、歩行時にふくらはぎが痛む間欠性跛行や、足の冷え・しびれなどが現れることがあります。また重症化すると安静にしていても足の痛み(安静時疼痛)や、足先の傷が治らない潰瘍・壊疽(えそ)まで引き起こすこともあります。これらは血液が十分に行き届かず組織が酸欠状態になるためです。
無症状のうちからの対策が重要です。高血圧・脂質異常症・糖尿病・喫煙などはPADの危険因子で、PAD患者ではこれらを合併する率が非常に高くなっています(高血圧82%、脂質異常72%、糖尿病44%との報告)。症状がなくてもこれらのリスク管理(食事・運動療法や薬物治療)を行い、必要に応じてABI検査(足首上腕血圧比)などで血流状態をチェックすることが大切です。PADが進行すると生活の質(QOL)を著しく低下させるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中など全身の動脈硬化症による合併症で5年生存率が低下することも知られています。
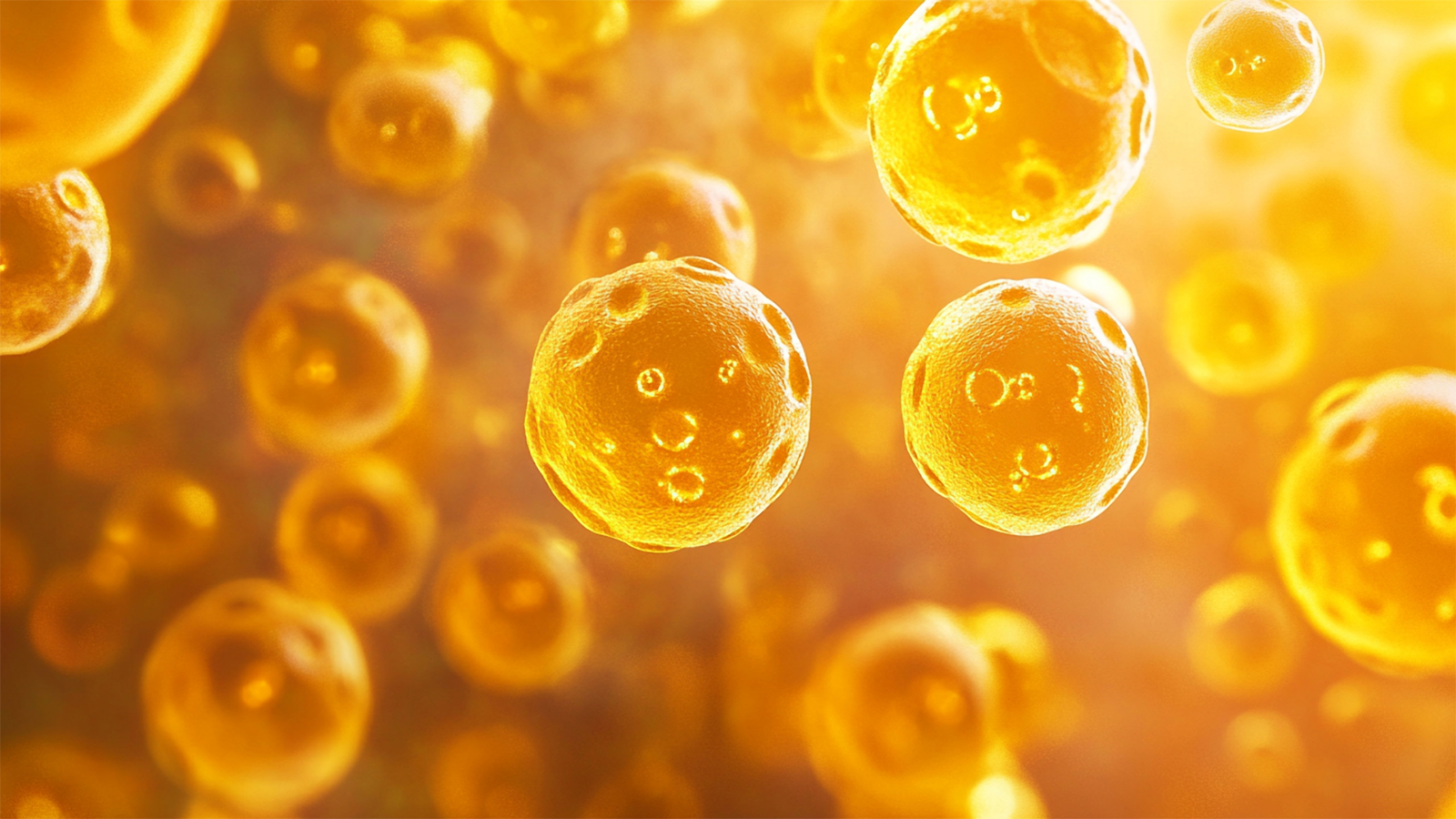
脂肪由来幹細胞(幹細胞)点滴療法とは?
脂肪由来幹細胞(Adipose-Derived Stem Cell)を使った治療は、ご自身の脂肪から取り出した幹細胞を培養して増やし、点滴で体内に戻す再生医療です。幹細胞とは体の中で他の細胞に成長(分化)できる細胞で、脂肪の他に骨髄や臍帯血などにも存在します。
特に幹細胞は皮下脂肪から比較的少量の採取で大量の幹細胞を得やすいのが特徴です。実際、腹部の皮下脂肪を少し採取して数週間かけ培養すると、1億個以上の幹細胞に増やすことが可能であり、この培養細胞を点滴で血管内に戻します。点滴自体は腕の静脈から行い、通常1時間程度で終了します。患者さん自身の細胞を用いるため拒絶反応の心配もありません。
投与量と回数: 現時点では明確な標準投与量や回数は定まっていませんが、多くの臨床研究では数千万~1億個程度の幹細胞を1回に点滴しています。必要に応じて細胞を凍結保存し、追加で再度点滴することも可能です。
幹細胞治療で期待できる効果
脂肪由来幹細胞を点滴すると、血流の悪く傷んだ組織に幹細胞が集まり組織修復に寄与します。具体的に患者さんにも分かりやすい効果として、次のような改善が報告されています。
- 足の痛みの軽減: 幹細胞療法により、安静時の足の痛みが和らぎ、歩行時の痛み(間欠性跛行)が改善します。例えばある研究では、治療後に痛みの強さがスコアで「6」から「1」まで大幅に軽減しました。
- 足の傷(潰瘍)の治癒促進: 血行不良で治らなかった足先の潰瘍が小さく縮まり、傷が治癒に向かう例が増えています。潰瘍サイズが縮小し、幹細胞投与を受けた患者さんの多数で潰瘍が改善しました。
- 歩行できる距離の延長: 幹細胞により筋肉への血流が改善することで、今までより長い距離を休まず歩けるようになります。実際に6分間歩行距離が平均255mから369mに延長したとの報告があります。
- 血流の再建(血管新生): 幹細胞治療後、足の血管が新たに形成されたり側副血行路が発達して、血液の巡りが良くなることが確認されています。血圧や酸素値の指標も改善し、ある解析では足関節のABIが平均+0.13、皮膚潅流圧(SPP)が+7 mmHg向上したと報告されています。血管造影検査でも治療前になかった細かい血管の描出がみられ、血行が蘇る再血管化が起こることを示しています。
このように幹細胞点滴療法は、痛みや歩行能力など患者さんのQOLを改善し、難治性の足潰瘍も治りやすくする可能性があります。さらに、重症化して壊疽に至るケースでは足の切断を減らす効果も期待されています。実際、幹細胞治療を受けた患者は従来治療のみの場合に比べ、足の切断率が約40%減少したとの解析結果も報告されています。
幹細胞はどうやって効くの?~作用メカニズム~
幹細胞がなぜこのような効果を発揮するのか、その背後にはマルチな作用メカニズムがあります。専門的にはいくつか挙げられますが、ポイントは次の通りです。
- 血管新生の促進: 幹細胞そのものや分泌する因子によって新しい毛細血管が形成されます。いわば幹細胞が「血管の種」となり、酸素や栄養を運ぶ新生血管ネットワークを作り出します。これにより血流不足だった患部にも血液が行き渡るようになります。
- 抗炎症・免疫調節作用: 脂肪幹細胞は炎症を鎮めるサイトカイン(タンパク質)を放出し、血管の炎症や腫れを抑える作用があります。動脈硬化で傷んだ血管壁の炎症が軽減すると、病状の進行を食い止める効果が期待できます。また免疫の働きを調節して、組織の治癒環境を整える役割も果たします。
- 組織・血管の修復: 幹細胞はダメージを受けた組織に集まり、そこで血管の内皮細胞などに分化して直接修復に寄与します。例えば傷ついた血管の内側(内皮)のコーティングを修復し、弾力や正常な機能を取り戻す手助けをします。さらに筋肉や皮膚の再生も促し、潰瘍など創傷の治癒も早めます。
- 成長因子のパラクリン作用: 幹細胞は上記の抗炎症物質だけでなく、血管や組織の再生を促す様々な成長因子(例えばVEGFやHGFといった因子)やエクソソームを周囲に放出します。これらが周辺の血管や細胞に作用し、間接的(パラクリン的)に再生を後押しします。いわば「幹細胞から出る傷の治癒を助けるお薬」のような働きです。
以上のように、幹細胞は“一粒で何役もこなす”治療役と言えます。単に血管を増やすだけでなく、悪化因子である炎症を抑え、壊れた組織を修復し、治癒促進物質をまき散らす――総合的な再生パワーによって下肢の血流障害を改善してくれるのです。
臨床研究が示す有効性と安全性
脂肪由来幹細胞療法は近年世界中で研究が進んでおり、中等症~重症PAD(特に他の治療手段がない重症虚血肢)の患者さんに対して有望な結果が報告されています。前述の通り症状改善効果が数多く報告されていますが、さらに重要なのはエビデンス(科学的根拠)です。
例えば、幹細胞療法の臨床試験をまとめたメタ分析(複数研究の統合解析)では、幹細胞を用いた群は従来治療のみの群に比べて潰瘍の治癒率が約1.7倍にも向上し、足の主要切断(大切断)の発生率も約41%低減したことが示されています。また無痛歩行距離(痛みなく歩ける距離)は幹細胞療法で平均約145m延長し、足関節血圧(ABI)も有意に改善するなど、客観指標でも治療効果が確認されています。特に重症例ではその恩恵が大きく、従来は治癒が難しかった難治性潰瘍が閉鎖し、血行再建により患肢を温存できたケースも多数報告されています。
日本においても、幹細胞点滴療法の多施設臨床研究(TACT-ADRC試験)が行われ、安全性と有効性が検証されています。この研究では、他に治療手段がない重症下肢虚血患者に自己脂肪由来幹細胞を足に投与しました。その結果、6か月後の生存率は100%、主要な足の切断回避率も94.1%と良好で、安静時疼痛の劇的な軽減や潰瘍の顕著な縮小が確認されています。有効率の高さに加え、重大な有害事象も認められず、安全に施行できたことが報告されています。世界的にも様々な臨床報告が蓄積されつつあり、専門家から「従来治療が効かないPADに対する有望な選択肢」として期待が寄せられています。
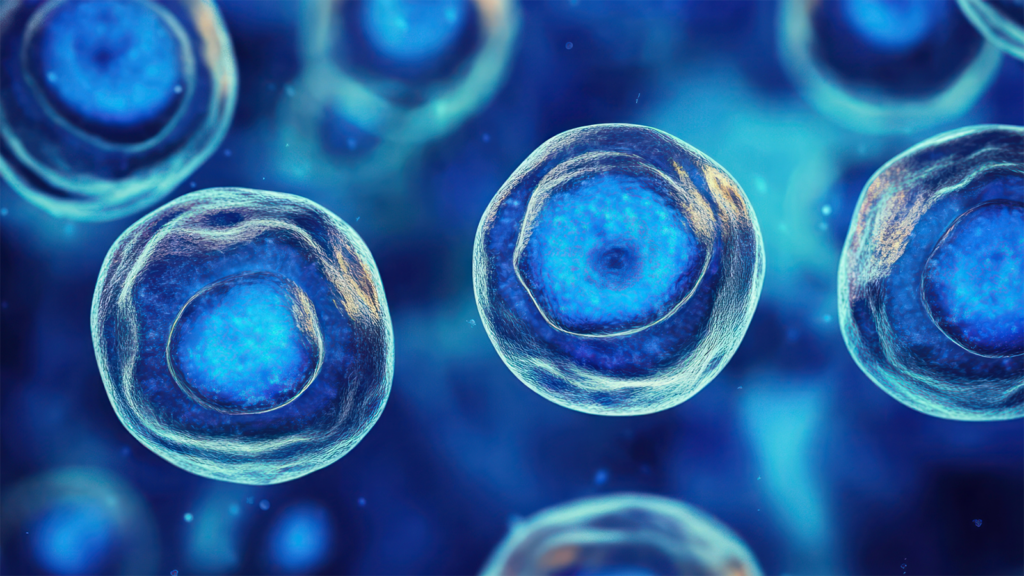
効果はどのくらい持続するの?
幹細胞治療による改善効果は比較的長期に持続することが多いとされています。多くの臨床試験では治療後6か月~1年のフォロー期間で観察していますが、その期間中症状の再悪化や効果減弱は少なく、効果が維持される例が報告されています。実際、上記の日本の試験でも少なくとも6か月時点で有意な改善が認められ、その後の経過でも潰瘍の再発や疼痛悪化なく経過した患者が大半でした。
ただし動脈硬化そのものが根治するわけではないため、時間とともに病態が進行したり他の血管が詰まれば再度症状が出る可能性はあります。効果の持続には個人差もあり、今後さらなる長期追跡データの蓄積が望まれています。幹細胞治療で得られた改善を長持ちさせるためにも、生活習慣の改善や薬物療法による動脈硬化対策を引き続き行うことが重要です。
安全性と副作用について
幹細胞点滴療法は自分自身の細胞を使う自家移植であるため、拒絶反応による深刻な副作用は基本的に起こりません。過去の臨床研究でも深刻な合併症の発生は稀であり、安全に施行できる治療法と考えられています。ただし医療行為である以上、起こり得るリスクについて知っておきましょう。
一般的な副作用・合併症としては、脂肪採取の際に局所麻酔を行うため、その麻酔へのアレルギーがまれに問題となる場合があります。脂肪を採取した部位に腫れや内出血、痛みが生じることもあります。点滴で細胞を戻した後は、一時的に発熱するケースが報告されていますが、大半は24時間以内に解熱しています。発熱が強い場合は解熱剤の投与など対症療法で対応します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 下肢閉塞性動脈硬化症(PAD)に気づくきっかけは何ですか?
A. 歩くとふくらはぎが痛くなり、休むと治る(間欠性跛行)症状が初期の典型です。しかし、症状がない場合も多いため、高血圧や糖尿病がある方は定期的に検査を受けることをおすすめします。
Q2. 幹細胞療法は保険が適用されますか?
A. 現在のところ、脂肪由来幹細胞療法は自由診療(保険適用外)となっています。費用はクリニックによって異なるため、受診時に確認しましょう。
Q3. 治療に使用する脂肪はどれくらい採取しますか?
A. 通常はお腹や太ももから少量(数ml、パチンコ玉程度)の脂肪を局所麻酔下で採取します。美容整形での脂肪吸引より遥かに少量ですので、身体への負担も軽く済みます。
Q4. 一度治療を受けたら効果は一生続きますか?
A. 幹細胞治療は長期にわたり症状改善が持続する場合がありますが、動脈硬化そのものを完全に治すわけではありません。効果を維持するためには、生活習慣改善や定期的なメンテナンスが重要です。
Q5. 幹細胞点滴療法は痛いですか?
A. 点滴自体は通常の点滴と変わらず、特別な痛みはありません。ただし、脂肪採取時に局所麻酔を使用するため、その際に軽い痛みや腫れが生じることがあります。
Q6. 幹細胞点滴の副作用やリスクはありますか?
A. 自分の細胞を用いるため拒絶反応は起こりませんが、まれに脂肪採取部位の内出血や点滴後の軽い発熱があります。これらは一時的で、ほとんどが自然に治まります。
Q7. 幹細胞治療を受けられない人はいますか?
A. 活動性のがんをお持ちの方、重度の感染症や全身状態が不安定な方は治療が難しい場合があります。医師の診察を受けて適応を判断します。
Q8. 効果はどれくらいで実感できますか?
A. 個人差はありますが、多くの方は治療後数週間~数か月で歩行距離の延長や痛みの軽減などの効果を実感されています。
Q9. 点滴療法とカテーテル治療の違いは何ですか?
A. カテーテル治療は血管内を直接物理的に拡げる治療法であり、幹細胞点滴療法は血管の再生を促す治療法です。重症度や血管の状態によって使い分けたり併用します。
Q10. 幹細胞治療後に日常生活で気をつけることはありますか?
A. 治療後も禁煙、適度な運動、食生活の改善、薬物治療を継続することで動脈硬化の進行を防ぎ、治療効果をより長持ちさせることができます。
まとめ
中等症の閉塞性動脈硬化症(PAD)で「歩くと足が痛い」「足先の傷が治りにくい」といった症状にお悩みの方にとって、培養拡大した自己脂肪由来幹細胞の点滴療法は新たな希望となりつつあります。動脈硬化で不足した血流を患者さん自身の細胞の力で回復させるこの再生医療は、潰瘍の改善や疼痛軽減、歩行能力向上など生活の質を大きく向上させるポテンシャルを示しています。
従来のカテーテル治療やバイパス手術が難しいケースでも、自分の細胞ならではの安全性を保ちながら治療の道を開くことが期待されています。もっとも万能の治療ではないため、他の治療や生活習慣改善との併用が重要ですが、「自分の細胞で治す」未来型の治療は確実に現実味を帯びてきています。
今後さらに研究が進めば、効果や適応の範囲も明確になり、より多くの患者さんがこの恩恵を受けられるようになるでしょう。動脈硬化が引き起こす足の血流障害に対し、新たな選択肢としての脂肪由来幹細胞治療は、患者さんに笑顔と歩く力を取り戻す可能性を秘めています。
参考文献(Vancouverスタイル)
1. Ribeiro M. Advances in Cell-based therapies for peripheral arterial disease. Tissue Cell. 2025;95:102909.
2. Shimizu Y, Kondo K, Ebisawa S, et al. Therapeutic angiogenesis for patients with no-option critical limb ischemia by adipose-derived regenerative cells: TACT-ADRC multicenter trial. Angiogenesis. 2022;25(4):535-546.
3. Xie B, Luo X, Shao L, et al. Autologous stem cell therapy in critical limb ischemia: A meta-analysis of randomized controlled trials. Stem Cells Int. 2018;2018:7528464.
4. Tseng SL, et al. Adipose-derived stem cells in diabetic foot care: Bridging clinical trials and practical application. World J Diabetes. 2024;15(6):1162-1177.







とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)




