自己脂肪由来幹細胞(ADSC)とは何か?
ADSCは自分の脂肪組織から採取される幹細胞で、再生医療の分野で注目されています。ご自身のお腹などの脂肪から比較的容易に分離でき、他人の幹細胞と比べ拒絶反応も起こりにくい特長があります。ADSCはさまざまな組織の細胞に分化する能力と、サイトカインや成長因子など多くの有益な物質を分泌する能力があります。この分泌物にはエクソソームと呼ばれる極小の小胞も含まれ、これらが周囲の細胞に働きかけて炎症を抑えたり血管の新生を促したりします。
糖尿病では高血糖により全身の血管や神経にダメージが蓄積し、様々な合併症(網膜症・腎症・神経障害、足の潰瘍や壊疽など)を引き起こします。近年、このADSCを体に戻す治療(点滴注射や患部への局所注射)が、糖尿病の合併症を改善する新しい手段として研究されています。以下では主に2型糖尿病(1型にも応用可能)の代表的な合併症について、ADSC単独療法やADSC由来エクソソーム療法のヒト臨床試験にもとづく最新エビデンスと、そのメカニズムをご紹介します。
糖尿病足潰瘍・壊疽への効果(創傷治癒の促進)
糖尿病性足潰瘍(いわゆる「足の壊疽」を含む)は、糖尿病患者さんの足に生じる難治性の傷で、悪化すると足の切断にも至りうる重症合併症です。現状の治療(デブリドマンや創傷被覆材、血行再建など)でも治らない慢性潰瘍に対し、自分の脂肪由来幹細胞を患部に注射する治療が試みられています。最近の臨床研究では画期的な創面閉鎖率が報告されています。
例えば2021年に報告された研究では、慢性足潰瘍で切断寸前の患者63名に対しADSCを多く含む自己脂肪組織由来の細胞集団(SVF)を足の潰瘍周囲に単回注射しました。その結果、6か月で51人(81%)が完全に傷が治癒し、8人も75%以上改善しました。12か月時点でも50人(79%)が完全治癒を維持し、ほとんどの患者で潰瘍面積の大幅縮小が続いています。治療後にドップラー検査を行うと、足の動脈血流が有意に改善しており、新生血管による循環改善が示唆されました。実際、注入した幹細胞により潰瘍部位で毛細血管が再生し、壊死していた腱が新しい組織で覆われるケースも観察されています 。さらに別の試験では、注射から6年後の長期経過でも半数の患者で潰瘍再発防止など効果の持続が確認されています。
ADSCが糖尿病足潰瘍を治癒に導く主なメカニズム(抗炎症作用・血管新生促進・表皮再生の促進)
糖尿病による足潰瘍では血行不全と組織修復力の低下が問題となるが、ADSCは傷周囲でサイトカインや成長因子(VEGFなど)を放出し、新たな毛細血管の形成(血流改善)や皮膚の再生を促進する。また免疫細胞に作用して慢性炎症を鎮め、組織破壊を食い止める。こうした多面的効果により難治性潰瘍の根本治癒を促すと考えられている。
こうした治療効果の背景には、ADSCの多角的な作用メカニズムがあります。
ADSCは傷の部位で血管内皮増殖因子(VEGF)や塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF)などを放出し、新しい血管の形成を促します。これにより患部の血流が改善し、酸素や栄養が行き届いて治癒力が高まるのです。また、ADSCは皮膚の基底にあるケラチノサイト(表皮細胞)や線維芽細胞の増殖を助け、傷口の表皮化(皮膚で覆うこと)を促進します。
さらに免疫調節作用も重要です。
ADSCは炎症を悪化させるマクロファージM1型を沈静化し、修復を促すM2型へと誘導したり、T細胞のバランスを整えて慢性的な炎症反応を抑制します。つまり、ADSC療法は「血行再建」「組織再生」「炎症制御」を同時に実現する包括的アプローチであり、単に傷を覆う従来ケアとは一線を画す根本的治療になり得ると期待されています。効果を最大にする治療タイミングについて明確な基準はまだありませんが、「重症化してからでも効果が見られる」ことが上記研究で示された一方、専門家は早めに介入するほど潰瘍悪化や切断を防げる可能性が高いと指摘しています。現在、世界中で数十件の臨床試験が進行中であり、ADSC療法は糖尿病足病変の治療に大きな変革をもたらす可能性があります。

糖尿病性腎症(腎障害)への効果(腎機能の保護)
糖尿病性腎症は、糖尿病による腎臓の細小血管障害で、進行すると慢性腎不全から透析療法が必要になります。現在は血糖・血圧コントロールや薬物(RAS阻害薬など)で進行抑制を図りますが、腎機能が低下し始めると元に戻す治療法はありません。そのような中、ADSCを用いた再生療法が腎機能低下を食い止める新たな戦略として研究されています。
ヒトを対象とした複数の初期臨床試験(主に2型糖尿病の患者対象)では、ADSCを点滴静注することで腎機能の指標であるGFRの低下を緩やかにする効果が示されています。例えばEUを中心に行われたNEPHSTROM試験(2023年発表のランダム化比較試験)では、進行腎症患者に臍帯由来MSCを点滴し18か月追跡したところ、MSC投与群はプラセボ群に比べeGFRの年間低下量が有意に小さく(腎機能悪化のスピードが遅い)、クレアチニン値や尿中微量アルブミンも改善傾向を示しました。従来治療では改善が難しい指標で効果が確認されたのは大きな前進です。
また安全性の面でも、副作用発生率はプラセボと差がなく、点滴後に免疫拒絶なども起こらなかったことが報告されています。別の臨床試験でも同様に、ADSC療法により糸球体濾過値(eGFR)がベースラインから向上・安定化する傾向が報告されており、これらを統合した最新の解析では、ADSCを含む間葉系幹細胞治療は糖尿病腎症患者の推算GFRや血清クレアチニンを有意に改善し、尿中アルブミン排泄の減少も認められると結論づけられています。
メカニズムとしては、ADSCが分泌する抗炎症サイトカインや微小RNAが腎臓内の慢性炎症反応と線維化(コラーゲン沈着)を抑制し、腎組織の傷害進行を食い止めると考えられます。実際、ADSCを投与した患者では炎症に関与する単球やT細胞の状態が安定化し、炎症制御に重要な制御性T細胞が保たれるなど免疫バランスの改善が確認されています。さらにADSCから分泌される種々の成長因子が腎臓の血流を改善し、障害された尿細管や糸球体の細胞修復を促進する可能性も示唆されています。
ただし、現時点の臨床研究は症例数が少なく観察期間も1~2年程度であるため、「腎症の進行を長期に渡って止められるか」「透析導入をどれだけ減らせるか」といった点は今後の大型試験で検証が必要です。治療タイミングについては、あまり腎不全が進みすぎた末期では効果が出にくい可能性があり、腎機能中等度低下(例:eGFR30~50程度)の段階で投与するのが望ましいと考えられています。将来的には、糖尿病腎症の新たな腎保護療法としてADSC点滴を定期的に行い、透析や腎移植を回避できるようになることが期待されています。
糖尿病網膜症への効果と安全性
糖尿病網膜症は、網膜の血管が傷み出血したり新生血管が増殖したりすることで視力低下をきたす合併症です。進行すると失明のリスクもあり、現在はレーザー光凝固術や抗VEGF薬の硝子体注射が主な治療法ですが、根本的に網膜の健康を取り戻す治療はありません。ADSCは網膜症に対しても保護的に働く可能性が報告されています。
動物モデルを用いた研究では、ADSCを目の周囲に移植したところ網膜の神経細胞の生存が促進され、視機能が改善するとの結果が得られました。例えば糖尿病モデルマウスの網膜にADSC由来の培養上清(分泌因子を含む液)を投与すると、網膜の炎症や酸化ストレスが軽減され、異常な血管増殖(新生血管)が抑えられたとの報告があります。この研究では実際に視力相当の指標(視覚機能)が向上するという有望な結果も示されています。ADSCが分泌するエクソソーム中のマイクロRNAやタンパク質が、網膜症の発症に関与するWnt/β-カテニン経路や炎症経路を抑制することも明らかになりつつあります。これらの作用により網膜の浮腫や出血を減らし、視力の維持に貢献すると考えられます。
しかしヒトにおける糖尿病網膜症へのADSC治療はまだ臨床研究段階であり、安全性に十分な注意が必要です。特に目への直接の幹細胞注射については慎重でなければなりません。動物実験ではADSC由来エクソソームを全身投与して網膜症状の改善を示す成果も出始めています。また、2025年現在、一部の国では糖尿病網膜症患者に対するADSC療法の臨床試験が開始されており、将来的にはエクソソーム点眼薬や注射薬による網膜保護が実現する可能性があります。糖尿病網膜症は「沈黙の進行」をする病気ですが、ADSC療法により早期から網膜を健康な状態に保ち、重症化を予防するようなアプローチが期待されています。ただし現時点では標準治療ではないため、患者さんは安易に未承認の幹細胞治療を受けることのないよう注意が必要です。
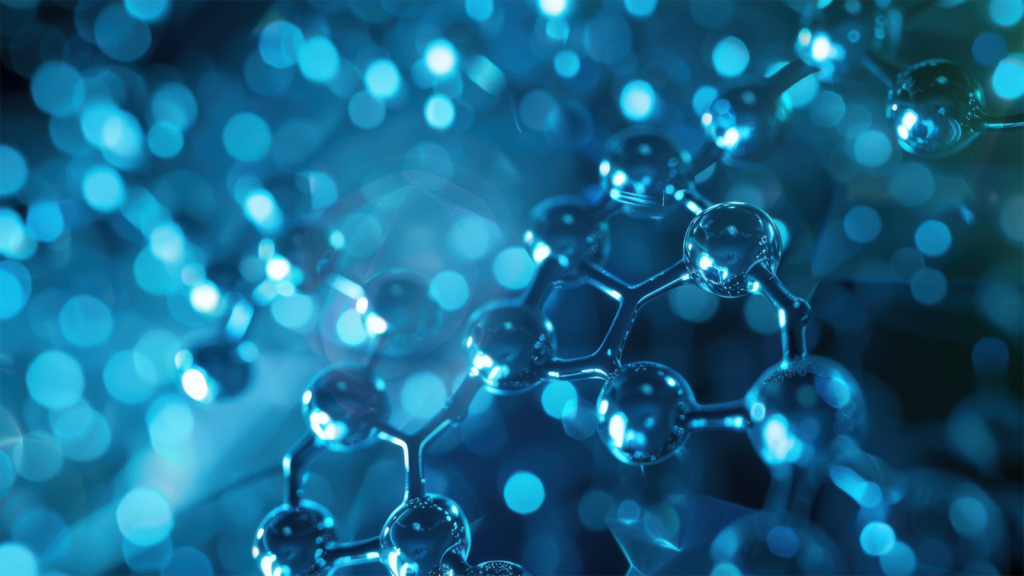
糖尿病神経障害への効果(神経再生と症状改善)
糖尿病性神経障害(ニューロパチー)は、手足の知覚低下や疼痛(しびれ・痛み)を引き起こす合併症で、足潰瘍の原因にもなります。現在、神経障害そのものを治す治療法はなく、痛みに対する対症療法(鎮痛薬やビタミン剤)が中心です。この難題に対し、ADSCを含む幹細胞療法が神経を再生させうる新たな治療として注目されています。幹細胞は損傷した神経組織の修復を促し、さらに血管新生と神経栄養因子の供給によって神経機能を回復させる作用があります。
実際、ヒトを対象とした臨床研究のメタ解析では、幹細胞療法を受けた糖尿病患者は受けていない患者に比べて神経伝導速度が有意に改善し、感覚障害や痛みのスコアも改善することが示されました。具体的には、運動神経伝導速度が平均2.2 m/s、感覚神経伝導速度が1.9 m/s向上し、振動覚閾値(ビリビリと感じる感覚の鈍さの指標)や総合的な神経症状スコア(トロントスコア)が有意に低下(改善)しています。加えて、患者さんが感じる痛みやしびれの軽減も報告されました。興味深いのは、こうした効果が比較的早期に現れる点です。ある小規模試験ではADSCの静脈投与後数週間で下肢の知覚が改善し始めた例もあります。副作用についても、報告されたのは注射部位の痛み・腫れといった一過性の軽症例のみで、幹細胞療法は神経障害の患者さんにも概ね安全に実施できています。
ADSCが神経障害を改善するメカニズムは複合的です。第一に、ADSCは損傷部位で神経栄養因子(NGFやBDNFなど)を放出し、傷ついた神経細胞の生存と軸索再生をサポートします。第二に、血管新生作用により神経への血液供給を増やし、虚血による神経ダメージを緩和します。第三に、慢性的な炎症反応を抑えることで神経周囲の有害な環境(神経を取り囲む支持組織の炎症・線維化)を改善します。実際、糖尿病マウスにMSC由来エクソソームを投与した実験では、末梢神経中の炎症性マクロファージが減少し、血管内皮の炎症活性も低下することが確認されています。
特にエクソソームに含まれる抗炎症microRNA(例:miR-146a)を強化することで、神経伝導の回復効果が飛躍的に向上するとの報告もあります。こうした知見から、今後はADSCそのものだけでなく、それが出すエクソソームを用いた神経障害治療も発展していくでしょう。例えば、現在糖尿病性足潰瘍に対してADSC由来エクソソームを含む外用薬を用いる臨床試験が進行中であり 、将来的には神経障害に対してもエクソソーム製剤を点滴や局所注射で投与することで、痛みのない神経再生治療が提供できるかもしれません。
以上のように、ADSC療法は糖尿病合併症の幅広い領域で有望な効果を示しています。その効果は単なる対症療法ではなく、傷んだ組織の修復や再生といった根本的な改善である点が画期的です。効果の持続性についても、足潰瘍では長期にわたり創傷閉鎖を維持できたり、腎症でも進行を遅らせ透析導入を先延ばしにできる可能性が示唆されました。ただし、現時点では多くが臨床試験段階であり、治療法として確立するには更なる検証が必要です。患者さん向けに言えば、「すぐに誰もが受けられる治療」ではないものの、将来に向けて非常に希望の持てる研究成果と言えます。引き続き世界中で大規模試験が行われ、安全性と有効性が確認されれば、5年後10年後には糖尿病の合併症予防・治療にADSCやそのエクソソームを活用する時代が来るかもしれません。
よくある質問(FAQ)
Q1. ADSC(自己脂肪由来幹細胞)とは具体的に何ですか?
A. ADSCはご自身のお腹や太ももの脂肪から採取される幹細胞で、様々な細胞に分化する能力と組織修復を促す物質(サイトカインや成長因子、エクソソーム)を分泌する能力を持っています。
Q2. ADSC治療は糖尿病のどんな合併症に効果がありますか?
A. 足の潰瘍や壊疽、腎症、神経障害、網膜症など糖尿病に伴う様々な合併症に改善効果が報告されています。特に難治性の足潰瘍には非常に有効な治療法として期待されています。
Q3. 足潰瘍に対するADSC療法はどれくらいの治癒効果がありますか?
A. 臨床研究では6か月以内に約80%が完全治癒し、治療から1年後も約80%で潰瘍が閉じた状態が維持されています。また新しい血管が形成され、血流が改善することも確認されています。
Q4. ADSC療法による糖尿病性腎症への効果はどれくらいですか?
A. 臨床試験ではADSCを点滴投与することで、腎機能の低下を有意に遅らせることが示されています。現状維持または改善傾向があり、透析導入を遅延できる可能性があります。
Q5. ADSC療法は糖尿病性神経障害にも有効ですか?
A. はい。幹細胞療法を受けた患者さんでは神経の伝導速度が改善し、しびれや痛みが軽減することが報告されています。神経再生作用や抗炎症作用などが複合的に働いて効果をもたらしています。
Q6. ADSCを用いた治療に副作用や安全面でのリスクはありますか?
A. 自分自身の細胞を使うため拒絶反応は基本的にありません。副作用は注射部位の軽度な痛みや腫れが一時的に起こる程度で、重篤な合併症は稀とされています。
Q7. 糖尿病網膜症にADSC治療はすでに実用化されていますか?
A. 網膜症へのADSC療法はまだ動物実験や初期の臨床研究段階です。ヒトでの安全性や有効性は今後の検証が必要ですが、将来的にエクソソーム製剤などを用いて早期介入する治療法が期待されています。
Q8. ADSC療法の治療効果はどれくらい持続しますか?
A. 足潰瘍治療では1年以上、場合によっては数年にわたり効果が維持されることが報告されています。腎症や神経障害では長期経過を観察する研究が進行中ですが、数ヶ月~数年単位で持続する可能性があります。
Q9. 治療を受ける最適なタイミングはありますか?
A. 足潰瘍は早期介入ほど予後が良いとされます。腎症では透析が必要になる直前(eGFR 30~50程度)が効果的です。いずれの合併症も重症化する前に治療開始するのが望ましいと考えられます。
Q10. 現在のところ、ADSC治療は一般的に受けられる治療法ですか?
A. 現在はまだ自由診療(保険外診療)の扱いで、一部の専門クリニックでのみ受けることが可能です。今後、安全性や効果がさらに確認されれば、より一般的な治療として広がる可能性があります。
参考文献リスト
1. Carstens MH, et al. (2021). Treatment of chronic diabetic foot ulcers with adipose‐derived stromal vascular fraction cell injections: Safety and evidence of efficacy at 1 year. Stem Cells Translational Medicine, 10(8):1138-1147 (New stem cell therapy shows promise to prevent diabetes-related amputations).
2. Liu X, et al. (2023). Safety and Preliminary Efficacy of Mesenchymal Stromal Cell (ORBCEL-M) Therapy in Diabetic Kidney Disease: A Randomized Clinical Trial (NEPHSTROM). J Am Soc Nephrol, 34(10):1733-1746.
3. Packham DK, et al. (2016). Allogeneic Mesenchymal Precursor Cells (MPC) in Diabetic Nephropathy: A Randomized, Placebo-controlled, Dose Escalation Study. EBioMedicine, 12:263-269.
4. Mikłosz A & Chabowski A. (2024). Efficacy of adipose-derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of chronic micro- and macrovascular complications of diabetes. Diabetes Obes Metab, 26(3):793-808.
5. Yan D, et al. (2024). Progress and application of adipose-derived stem cells in the treatment of diabetes and its complications. Stem Cell Res Ther, 15:3.
6. Rahimi-Movaghar V, et al. (2024). Human studies of the efficacy and safety of stem cells in the treatment of diabetic peripheral neuropathy: a systematic review and meta-analysis. Stem Cell Res Ther, 15:442).
7. Jurowski P, et al. (2025). Future Directions in Diabetic Retinopathy Treatment: Stem Cell Therapy, Nanotechnology, and PPARα Modulation. Int J Mol Sci, 26(4):1625.
8. Wu J, et al. (2022). Mesenchymal stem cell-derived exosomes: The dawn of diabetic wound healing. World J Diabetes, 13(12):1066-1095.







とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)




