自己脂肪幹細胞(ADSC)療法という選択肢
糖尿病を長く患っていると、「このまま悪化して失明したらどうしよう」「足にできた傷が治らず、最悪切断なんてことになったら…」といった不安が頭をよぎることはありませんか?40代以上の方なら、なおさら将来の合併症が心配になるでしょう。
そんな糖尿病の合併症を、自分自身の細胞の力で食い止めようという最先端の再生医療があります。それが 自己脂肪由来幹細胞(ADSC)療法 です。自分のお腹まわりの脂肪から取り出した幹細胞を使って、体の中から血管や組織を修復し、合併症の改善や血糖コントロールの向上を目指す治療法で、まさに「自分の細胞がドクターになる」ようなアプローチです。
糖尿病では血糖値が高い状態が続くことで、全身の血管や神経にダメージが蓄積し、糖尿病網膜(目)・糖尿病腎症(腎臓)・糖尿病神経障害(神経)・足の潰瘍や壊疽(足)といった様々な合併症を引き起こします。ADSC療法は、このような複数の合併症に対して、私たち自身の細胞を用いた“体の修理”で立ち向かう新しい戦略です。では一体ADSCとは何者で、どのように作用し、どんな効果が得られているのでしょうか?専門的な話になりがちな再生医療ですが、できるだけ分かりやすく、身近なたとえも交えながらご紹介します。

ADSCって何?自分の脂肪から採れる「修理屋さん」細胞
ADSC(自己脂肪由来幹細胞) とは、その名のとおり自分自身の脂肪組織から取り出した幹細胞です。幹細胞とは様々な細胞に分化する能力を持つ「もとになる細胞」で、ADSCは脂肪から比較的簡単に採取できるうえに、他人の細胞を使う場合と比べて拒絶反応も起こりにくいという利点があります。お腹や太ももなどに少し脂肪がついている方なら、その「予備の脂肪」が将来「体を修理する素材」になるかもしれないのです。
ADSCは、必要に応じて血管や神経、皮膚など様々な組織の細胞に育つことができるだけでなく、周囲の細胞に働きかける有益な物質(サイトカインや成長因子など)をたくさん分泌するのが特長です。中でもエクソソームと呼ばれる微小な小胞に包まれた物質は、ADSCからの「メッセージ」としてダメージを受けた組織の修復を強力に後押しします。つまりADSCは、「自分の体から採れた修理屋さん」のような存在なのです。
現在、このADSCを体に点滴したり患部に注射したりして戻す再生医療が、糖尿病によるさまざまな合併症を改善する方法として注目されています。では、ADSCは具体的にどんな仕組みで作用するのでしょうか?次にそのメカニズムを見てみましょう。
ADSCの作用メカニズム – 血管を再生し、炎症を抑え、組織をよみがえらせる
糖尿病の合併症では、傷ついた組織で血流不足と慢性的な炎症が起き、治る力が弱まっていることが多いです。ADSCは、まるで植物に水と肥料を与える園芸家のように、ダメージを受けた組織に対して次のような働きをします。
- 血管新生(新しい血管を作る) – 組織の周りに VEGF(血管内皮増殖因子)や bFGF(線維芽細胞増殖因子)などの成長因子を放出し、細くなった血管の代わりに新しい毛細血管を育てて血流を改善します。血液という名の「水路」が新設されることで、酸素や栄養が行き届き、組織の治癒力が取り戻されます。
- 抗炎症(炎症を鎮める) – ダメージ部位に集まっている免疫細胞(マクロファージやT細胞など)に作用して、その過剰な攻撃反応を落ち着かせます。いわばくすぶる炎症という名の火事を消火し、組織破壊の連鎖を食い止めます。例えばADSCは炎症を促進するマクロファージ(M1型)を修復モードのマクロファージ(M2型)へと性質変換させたり、炎症性のサイトカイン(TNF-αやインターロイキン)を減少させたりします。慢性炎症が収まれば、組織は治る環境を取り戻します。
- 組織再生(新しい細胞で補修) – 損傷した部位で、皮膚のケラチノサイト(表皮細胞)や線維芽細胞の増殖を助けて傷口の皮ふを再生したり、傷んだ神経細胞の軸索(びゅんと伸びる配線部分)を修復したりします。つまり壊れた部品を新しいもので取り換えるような役割です。ADSC自身が分化して新しい細胞になることもありますし、前述のエクソソームなどを介して「修理を促す司令」を出すこともあります。
このようにADSC療法は「血行再建」・「炎症制御」・「組織再生」を同時に実現する包括的アプローチであり、いわば体内に“修理チーム”を送り込んで根本から治そうという発想です。従来の対症療法(例えば傷口を消毒して覆うだけ、痛みに薬を出すだけ)とは一線を画し、傷んだ組織そのものをよみがえらせる点が画期的だと言えます。では、実際にどのような合併症でどんな効果が確認されているのでしょうか?以下で具体的に見ていきましょう。
糖尿病足潰瘍(足の壊疽) – 傷を治し、失われかけた足を救う希望
糖尿病足潰瘍(足の壊疽を含む)は、足にできた傷がなかなか治らずに広がっていく合併症です。重症化すると感染や壊死が進み、足の一部を切断せざるを得ないケースもあります。高齢の糖尿病患者さんにとって、足を失うことは行動範囲や生活の質に大きな影響を及ぼすため、なんとか予防・治療したい合併症の一つです。ところが現在の標準治療(傷の洗浄や消毒、壊死組織の除去、血行再建手術など)を尽くしても治らない慢性潰瘍が少なくありません。そんな難治性の傷に対して、自分の脂肪から採取した幹細胞を患部に直接注射する治療が試みられています。まるで荒れ果てた畑に良質な苗を植えるように、傷口周辺にADSCを送り込んで再生を促すのです。
実際、近年の臨床研究では驚くべき傷の治癒率が報告されています。例えば2021年の研究では、通常の治療では治らず切断寸前だった慢性足潰瘍の患者63名を対象に、脂肪から抽出した細胞群(ADSCを豊富に含む間質血管分画:SVF)を潰瘍の周囲に1回注射しました。その結果、6か月後に51名(81%)の傷が完全に治癒し、さらに8名も75%以上の創面縮小という大幅な改善が見られたのです。12か月経過後も79%で完全治癒が維持されており、再発することなく傷が塞がったまま保たれました。ほとんどの患者で潰瘍面積が治療前より大幅に小さくなり、皮膚が再生している様子が確認されています。この治療では患者さん自身「もう歩けなくなるかもしれない」という不安を抱えていましたが、治療後には傷が閉じ、切断を免れただけでなく、自分の足で歩ける喜びを取り戻したのです。まさに自分の細胞が足を救ったと言えるでしょう。
治癒率の高さだけでなく、ADSCが患部の血行を大幅に改善していた点も見逃せません。治療後に足の血流を調べる超音波(ドップラー)検査を行ったところ、患足の動脈血流が有意に増加しており、新しく形成された血管によって循環が良くなったことが示唆されました。実際に潰瘍部位の生検では、新生毛細血管の増生や、露出して壊死していた腱が新しい肉芽組織で覆われていく様子も観察されています。ADSCが放出するVEGFなどの作用で血管網が再建され、酸素と栄養が隅々まで行き渡った結果、傷が自力でふさがる力を取り戻したのです。また別の臨床試験では、単回のADSC注射から6年経過した長期フォローでも、約半数の患者で潰瘍の再発防止など効果の持続が確認されました。このように、一度のADSC治療で得られた改善効果が何年も続く可能性が示されたことは、大きな希望と言えるでしょう。
どうしてADSCでここまで傷が治るの?
そのメカニズムは先ほど述べた通りですが、改めて足潰瘍のケースに当てはめてみます。糖尿病の足潰瘍では血流不足と組織の修復力低下が深刻ですが、ADSCを注射すると傷の周囲で血管新生が促されて血液の通り道が増え、患部に酸素と栄養が届きやすくなります。同時に皮膚や軟部組織の細胞増殖が刺激されて、新しい皮ふや肉芽組織が傷口を覆っていきます。さらに慢性的に続いていた炎症反応がADSCの作用で沈静化し、組織を破壊するような悪循環が断ち切られます。こうした三位一体の効果によって、「もう治らない」とあきらめかけていた傷が根本から治癒に向かうと考えられています。従来の治療が「傷を消毒して保護する」対症療法だったのに対し、ADSC療法は「傷そのものを治してしまう」根治療法になり得る点が画期的です。
もちろん全てのケースで魔法のように効くとは限りませんが、専門家によれば「重症化してからでも効果が見られる一方で、できるだけ早めに介入した方が潰瘍の悪化や切断を防げる可能性が高い」と指摘されています。足に慢性潰瘍をお持ちの患者さんにとって、ADSC療法は切断を回避し、自分の足で歩く未来を取り戻す希望になりつつあります。現在世界中で数多くの臨床試験が進行中であり、この療法が糖尿病足病変の治療に大きな変革をもたらす日はそう遠くないかもしれません。
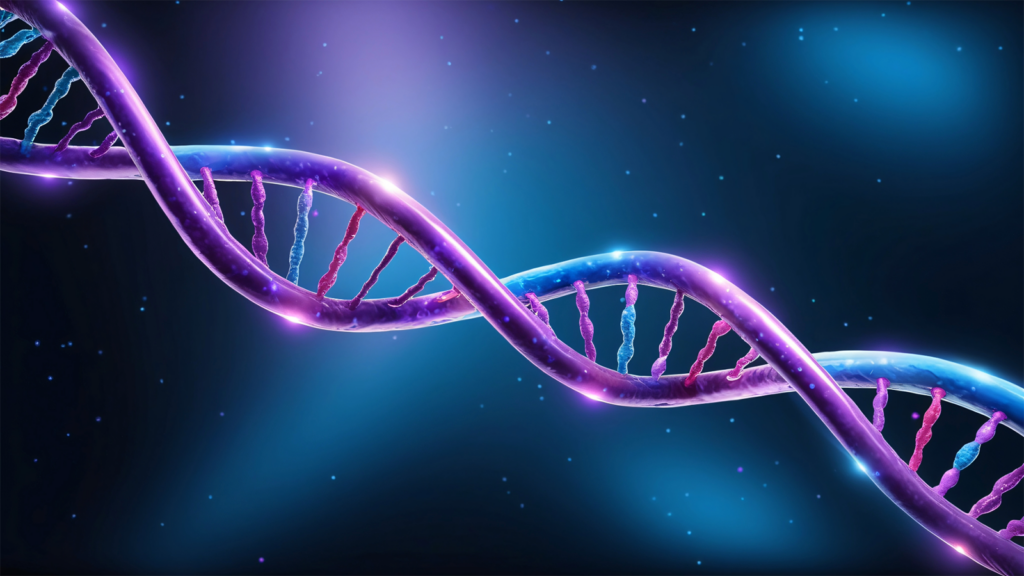
糖尿病性腎症(腎障害) – 腎臓を守り、透析を遠ざける
糖尿病性腎症は、糖尿病による腎臓内の細かな血管障害が進行し、やがて腎臓の機能が低下していく合併症です。悪化すると慢性腎不全となり、最終的には人工透析が必要になることもあります。腎症は進行を完全に止める有効策が乏しく、「このままだといずれ透析になります」と宣告されると患者さんにとって大きな心理的負担となります。現状では、血糖コントロールや血圧管理、ARB・ACE阻害薬といった腎保護効果のある薬で何とか腎臓の悪化スピードを抑えるのが精一杯で、一度落ちてしまった腎機能を回復させる治療法はありません。そうした中、自分の幹細胞の力で腎機能の低下を食い止めようという画期的な試みが進められています。
具体的には、ADSCを点滴静注(IV投与)することで全身を巡らせ、腎臓のフィルターである糸球体や尿細管のダメージを抑制しようというアプローチです。2010年代後半から世界各地で少人数の臨床研究が行われ始め、近年ようやくその効果を統合的に評価する段階に入ってきました。最新のエビデンスとして注目されるのが、EUを中心に実施されたNEPHSTROM試験です。
これは進行期の糖尿病性腎症患者に対し、ADSCの仲間である臍帯由来の間葉系幹細胞(MSC)を点滴投与し、その後18か月にわたって経過を追ったプラセボ対照試験(ランダム化比較試験)です。結果は非常に明るいものでした。MSCを投与されたグループでは、何もしなかったグループに比べて腎機能(eGFR)の年間低下量が明らかに小さく、腎機能悪化のスピードが有意に遅延したのです。さらに腎臓の老廃物を示す血中クレアチニン値の上昇や、尿中アルブミン排泄量の増加も抑えられる傾向が見られました。従来の治療では改善が難しかった指標において有意差が出たことは、大きな前進です。また安全性の面でも朗報がありました。重篤な副作用は見られず、点滴後に免疫拒絶反応なども起こらなかったことが確認されたのです。つまり、自分以外のドナー由来細胞を使っても安全に投与でき、腎機能悪化を遅らせる効果が示されたわけです。
さらに別の研究(オーストラリアでの臨床試験)でも、ADSC療法によってeGFRがベースラインから改善・安定化する傾向が報告されており、最新の解析を総合すると間葉系幹細胞(ADSCを含む)による治療は糖尿病腎症患者のeGFR低下を有意に抑制し、血清クレアチニンを改善、尿中アルブミン排泄を減少させると結論付けられています。これは2024年時点で発表された包括的な知見で、エビデンスの蓄積に伴い幹細胞療法の有効性に確信が高まりつつあることを示します。
ADSCが腎臓にどう作用するの?
その鍵はやはり抗炎症と組織修復です。糖尿病腎症では高血糖や代謝異常により腎臓に炎症反応が続き、組織が線維化(コラーゲン沈着による硬化)していきます。ADSCはそれを食い止めるように、炎症を鎮め抗線維化作用を発揮すると考えられています。実際、ADSC投与を受けた患者では、血液中の炎症性の単球やT細胞の暴走が抑えられ、炎症を抑える役割の制御性T細胞がしっかり維持されるなど、免疫バランスの改善が確認されています。さらにADSCの分泌する様々な成長因子が腎臓内の血流を改善し、傷ついた尿細管や糸球体の細胞修復を促す可能性も示唆されています。つまり、腎臓というフィルター装置のフィルター目詰まりや炎症を、ADSCが掃除・メンテナンスしてくれるイメージです。
とはいえ、現時点の臨床研究は症例数がまだ少なく、観察期間も1~2年程度と限られています。「腎症の進行を長期にわたって完全に止められるか」「透析導入をどれだけ回避できるか」といった 本当に患者さんが知りたいポイントは、今後の大型試験で検証が必要です。専門家の見解では、末期腎不全に至って腎臓の大部分が固まってしまった状態では効果が出にくい可能性があるため、eGFRが30~50程度の中等度の段階で投与するのが望ましいと言われます。将来的には、「透析一歩手前であってもADSC点滴で腎機能を守り抜き、透析や腎移植を遠ざける」そんな新たな腎保護療法として確立されることが期待されています。腎症でお悩みの患者さんにとって、ADSC療法は透析という大きな壁を先送りし、もしくは回避できるかもしれない希望の光となりつつあります。
糖尿病性神経障害 – 痛みやしびれを和らげ、神経の再生を促す
糖尿病性神経障害(ニューロパチー)は、手足の感覚低下やビリビリとした痛み・しびれを引き起こす合併症です。感覚が鈍くなることで足の傷に気づかず潰瘍が悪化する原因にもなりますし、逆に激しい神経痛が続いて夜も眠れないという方もいます。ところが現在、この神経障害そのものを治す根本治療はなく、痛みに対する鎮痛薬やビタミン剤などの対症療法が中心です。いつ終わるとも知れない痛み・しびれと付き合う毎日に、「もう治らないのだろうか…」と不安とストレスを抱える患者さんも少なくありません。
そんな難題に対し、ADSCを含む幹細胞療法が傷んだ神経を再生しうる新たな治療として期待されています。ADSCなどの幹細胞は、ダメージを受けた神経組織に寄り添ってその修復を促し、さらに周囲に新しい血管を作って神経に栄養と酸素を送り届けるサポーターとして働きます。加えて、炎症を抑える作用もあるため、神経周囲で起きている有害な炎症環境を改善する効果もあります。要するに、壊れた通信ケーブル(神経線維)を修理し、そのケーブルに電力を供給する電線(血管)も敷設し、ノイズの原因となる火事(炎症)も消してあげる――ADSCにはそんなトリプルの役割が期待できるのです。
実際の臨床成績も、この期待を裏付けています。最近発表された複数の研究を統合したメタ解析によると、糖尿病患者さんで幹細胞療法(ADSCを含む)を受けたグループは、従来治療のみのグループに比べて神経伝導速度が有意に改善し、手足の感覚障害や痛みのスコアも改善したことが示されました。具体的には、幹細胞療法により運動神経伝導速度が平均2.2 m/s、感覚神経伝導速度が1.9 m/s向上し、振動覚閾値(音叉で振動を感じる検査の指標)の低下や、神経症状の総合評価スコア(トロントスコア)の改善が認められています。
難治の神経痛に苦しんでいた患者さんたちが、「あれ、最近足のジンジンが和らいできたかも?」と感じ始める――そんな変化が客観的データにも表れたのです。また多くの患者さんで痛みやしびれの自覚症状が軽減し、夜まともに眠れなかった神経痛が和らいだとの報告もあります。興味深いことに、こうした効果は比較的早い時期に現れる傾向があります。ある小規模試験では、ADSCの静脈投与後わずか数週間で下肢の知覚が改善し始めた例もありました。副作用についても心配されるところですが、報告されたのは注射部位の痛み・腫れといった一過性で軽度なもののみで、全身的な重篤副作用はほとんど見られていません。つまり、ADSC療法は神経障害の患者さんにも概ね安全に実施できるということです。
効果が早めに現れる背景には、ADSCが神経を直接“元気づける”栄養因子を出してくれることが挙げられます。ADSCは損傷部位で NGF(神経成長因子)や BDNF(脳由来神経栄養因子)など多数の神経栄養因子を分泌し、傷ついた神経細胞の生存と軸索再生を助けます。ちょうど枯れかけた植物に栄養剤を与えるように、神経に必要な物質を届けてくれるのです。
第二に、前述の血管新生作用があります。新しい毛細血管網が神経周囲に張り巡らされると、慢性的な虚血(血流不足)に陥っていた神経に血が通い出し、エネルギー供給が改善します。その結果、ダメージの進行が緩和されます。
第三に、抗炎症作用も重要です。糖尿病性ニューロパチーでは神経を取り囲む支持組織にも炎症や線維化が起こって神経機能を妨げますが、ADSCはその慢性的な炎症反応を鎮めて組織環境を整えます。実際、糖尿病マウスにMSC由来のエクソソームを投与した実験では、末梢神経内の炎症性マクロファージが減少し、血管の内皮細胞における炎症も軽減しました。特にエクソソーム中の抗炎症マイクロRNA(miR-146aなど)に着目すると、神経の伝導機能回復効果が飛躍的に向上することも報告されています。このような知見から、今後はADSCそのものに加えて、それが出す「エクソソーム」を使った神経障害の治療も発展していくと考えられます。
例えば現在、糖尿病性足潰瘍に対してADSC由来エクソソームを含む外用薬(軟膏)を用いる臨床試験が進行中ですが、将来的には神経障害に対してもエクソソーム製剤を点滴や局所注射で投与することで、痛みのない神経再生治療が提供できるかもしれません。
神経障害に苦しむ患者さんにとって、ADSC療法は「もう一度、自分の足で大地の感触を感じられるようになるかもしれない」という希望を与えてくれます。長年続いた足のビリビリする痛みが和らぎ、再びぐっすり眠れる夜が来たら――そんな日常生活の質(QOL)の向上こそ、再生医療が目指すゴールの一つです。幹細胞療法の進歩により、痛み止めを飲んで耐えるしかなかった神経障害に対しても、「治す」時代が訪れつつあります。
糖尿病網膜症 – 失明の不安に挑む最先端のアプローチ
糖尿病網膜症は、目の奥の網膜という部分の細小血管が傷んで出血したり、逆に異常な新生血管が増えて網膜を障害することで、視力低下を引き起こす合併症です。初期には自覚症状が乏しいため沈黙の進行をたどり、気づいた時には網膜に広範なダメージが及んでいることもあります。進行すると黄斑浮腫や増殖網膜症となり、最悪の場合失明に至ることもあります。
現在、網膜症に対してはレーザー光凝固術(網膜の弱い血管を焼き固める)や抗VEGF薬の硝子体注射(新生血管を抑える薬を目に注射する)が主な治療法ですが、これらはあくまで「出血や新生血管を抑えて視力の悪化を食い止める」対症的なアプローチです。ダメージを受けた網膜の組織そのものを元通りに健康な状態へ戻す根本治療ではありません。患者さんからすれば、「焼いたり注射したりではなく、網膜自体が元気になる治療があれば…」と思うのが本音でしょう。
ADSC療法は、その難しい願いを将来的にかなえてくれるかもしれません。実は網膜症に対しても、ADSCが網膜の神経細胞を保護・再生し、異常な血管増殖を抑える可能性が報告され始めています。もっとも人間での実証はこれからですが、いくつかの先行研究を見てみましょう。まず動物実験の段階ですが、成果が挙がっています。糖尿病モデルのマウスで、網膜にADSC由来の培養上清(ADSCが培養液中に出したサイトカインやエクソソームを含む液体)を投与する研究では、網膜の炎症反応や酸化ストレスが軽減し、異常な新生血管の増殖が抑制されました。その結果、実際に網膜機能を反映する視力相当の指標(網膜の電気的反応など)が改善するという有望なデータも得られています。
また別の動物研究では、ADSCを目の周囲に移植することで網膜の神経細胞の生存が促進され、視覚機能の維持につながるという結果も報告されています。ADSCが分泌するエクソソーム内のmicroRNAやタンパク質が、網膜症の発症に関与する Wnt/β-カテニン経路 や炎症経路をブロックすることも徐々に明らかになりつつあります。これにより網膜のむくみ(黄斑浮腫)や出血を減らし、網膜組織を保護して視力の維持に貢献すると考えられます。
では、人ではどうでしょうか。2025年現在、糖尿病網膜症に対するADSC療法は臨床研究段階であり、まだ確立した治療ではありません。特に目というデリケートな臓器への直接の幹細胞注射については、効果とともにリスク(例えば網膜剥離や眼内の腫瘍形成リスクなど)も慎重に評価する必要があります。
そのため、まずはADSC由来エクソソームなど“細胞を使わない”方法で網膜症に挑む試みも出てきました。実際、動物実験ではADSCのエクソソームを点滴で全身投与し、網膜の炎症を抑えて症状を改善することに成功したという報告もあります。さらに国際的には、糖尿病網膜症患者さんに対するADSC注射療法の臨床試験が一部の国で開始され始めています。日本でも今後、エクソソームを点眼薬や眼球注射薬として利用する研究が進むかもしれません。将来的には「インスリンのように、エクソソームの自己注射や点眼で網膜を早期から保護する」といったセルフケアが可能になるかもしれない、と夢が広がります。網膜症は自覚症状がないまま進行するため、ADSC療法によりまだ見えているうちから網膜を健康に保ち、重症化を予防するようなアプローチが理想です。
繰り返しになりますが、現時点(2025年)ではADSC療法は糖尿病網膜症に対する標準治療ではありません。一部の自由診療クリニック等で先進的な治療として提供されるケースもあるようですが、患者さんは安易に未承認の幹細胞治療を受けないよう注意する必要があります。大切な眼を守るには、まずは定期的な眼科検診と既存の治療(血糖・血圧コントロールや眼科処置)をきちんと受けることが基本です。そのうえで、「将来こんな治療ができるようになるかもしれない」という希望の情報としてADSC療法の動向を知っておいていただければと思います。
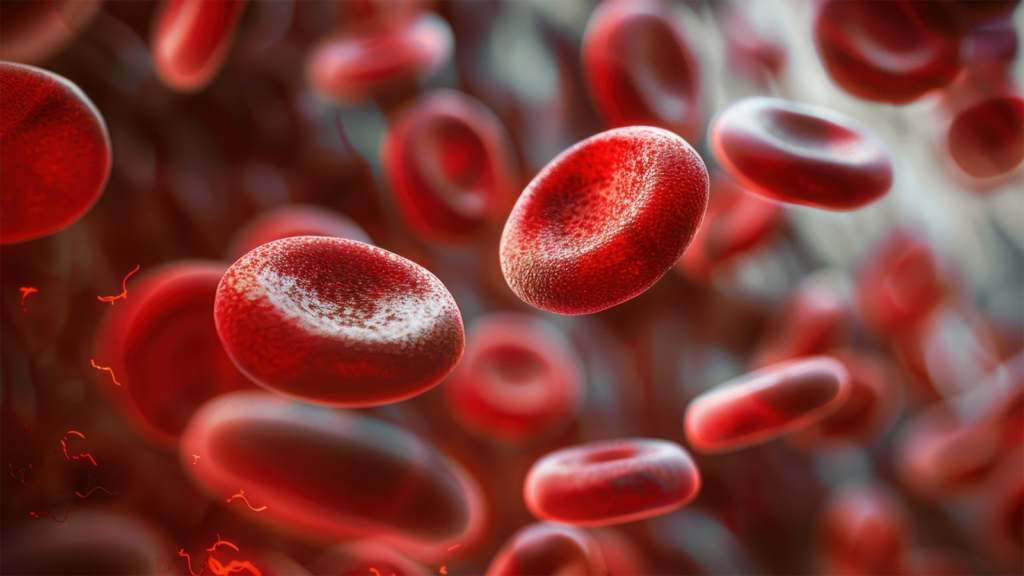
血糖コントロール への効果 – インスリンからの「卒業」も夢じゃない?
ここまで合併症への効果を見てきましたが、実はADSC療法には糖尿病そのもの、つまり血糖コントロールを改善する可能性も指摘されています。幹細胞は膵臓のインスリン産生細胞(β細胞)を保護・再生したり、全身のインスリン抵抗性を改善したりする作用があるためです。
糖尿病の動物モデルや初期のヒト臨床試験では、ADSCを投与することで体内のβ細胞が増えたり元気になったりし、さらに自己免疫反応を調整して残存しているβ細胞を守る効果が確認されています。その結果、インスリンの効きが良くなって血糖値が下がる(インスリン感受性の改善)ことが報告されています。言い換えれば、ADSC療法は合併症の修復だけでなく、糖尿病という病気の根幹にも働きかけている可能性があるのです。
実際いくつかの臨床研究で、HbA1c(ヘモグロビンA1c)が改善し、外部からのインスリン注射量を減らせたとの成果が報告されています。例えばある小規模試験では、ADSC治療後にHbA1cが治療前の約11%から6.7%にまで低下し、外因性インスリンの必要量も減少しました。また別のまとめでは、「糖尿病患者に対するADSC療法はHbA1c値とCペプチド値(膵臓から分泌されるインスリン量の指標)を改善し、必要なインスリン量を減らす」と有望な結果が示されています。
このように血糖コントロールの指標が良くなれば、将来的に内服薬やインスリン注射から「卒業」できる患者さんも出てくるかもしれません。
もっとも、血糖値の改善効果には個人差があると考えられ、重度の糖尿病で膵臓のβ細胞がほとんど残っていない方では劇的な変化は難しいかもしれません。しかし早い段階でADSC療法を併用することで、「今ある膵臓の働きをできるだけ長く保つ」ことや、「インスリン抵抗性を改善して合併症リスクを下げる」ことが期待できます。事実、ADSC投与後に炎症マーカーが低下しインスリン抵抗性が改善したという報告もあります。
糖尿病患者さんにとって、血糖コントロールが良くなることは合併症予防の基本であり、また日々の治療の負担軽減にもつながります。ADSC療法はその点でも、糖尿病との付き合い方を根本から変える可能性を秘めているのです。
治療の流れとスケジュール – 脂肪採取は1回、点滴は複数回、経過観察も万全に
ADSC療法に興味はあるけれど、「どんな手順で治療するの?痛みは?入院は必要?」といった疑問が湧くかもしれません。そこで最後に、一般的な治療スケジュールの一例をご紹介します。基本的な流れは 「脂肪を一度採取し、幹細胞を何度かに分けて点滴し、経過を定期的にフォローする」 というものです。
- 脂肪の採取(1回きり) – お腹や太ももなどから少量の脂肪組織を採取します。方法はミニ脂肪吸引のようなイメージで、局所麻酔下で数mL(パチンコ球)程度の脂肪を取ります。入院は不要で、日帰りで実施できます。所要時間は約30分程度です。採取した脂肪からADSCを含む細胞を分離・培養し、点滴できる状態に準備します(細胞加工には専門の施設と技術が必要です)。
- 幹細胞の点滴治療(複数回) – 点滴静脈注射によってADSCを体内に戻します。初回の脂肪採取で得られた細胞を分割し、計3~6回ほどに分けて投与するケースが多いです。例えば1~3か月おきに1回ずつ点滴を行い、合計3回コース、あるいは状態に応じて最大6回まで追加する、といったプロトコルが用いられます。点滴自体は約1時間程度で終了し、痛みもなく外来で受けられます。自分の細胞なので拒絶反応の心配も基本的にありません。
- 経過観察(定期フォローアップ) – 治療後は定期的に検査を行い、合併症の指標や症状がどう変化したかを評価します。例えば足潰瘍なら傷の大きさや血流の改善具合、腎症なら血液・尿検査で腎機能指標、神経障害なら知覚テストや痛みのスコア、網膜症なら眼底検査で所見を追います。効果が認められた場合はそのまま様子を見ますが、必要に応じて追加のADSC点滴を行うこともあります。なおフォロー期間中も糖尿病の通常治療(血糖・血圧コントロール等)は継続し、ADSC療法との相乗効果で合併症ケアをしていきます。
上述のように、ADSC療法は多少スケジュールの長い治療ではありますが、一度採取した脂肪から必要な細胞を確保できれば、繰り返し点滴を受ける際に追加の脂肪採取は不要です。治療を受ける患者さんの負担としては、「脂肪を取る処置」は1回きりで、その後は月に一度程度病院で点滴を受けるだけとなります。
点滴中はリクライニングチェアなどでリラックスして過ごせる場合が多く、痛みもほとんどありません。副作用も今のところ大きなものは報告されておらず、安全に配慮しながら行われています。ただし現段階では自由診療(保険適用外)の扱いとなるケースが多く、費用は高額になる傾向があります。そのため治療を検討する際は、クリニックで十分に話を聞き、リスクとベネフィット、費用面も含め納得したうえで判断することが大切です。
よくある質問(FAQ)
Q1. ADSC療法はどんな糖尿病患者さんが対象ですか?
A. 糖尿病による足潰瘍、腎症、神経障害、網膜症など合併症をお持ちの方や、血糖コントロールが困難な方が主な対象です。特に通常治療で改善が難しいケースで効果が期待されています。
Q2. 自分の脂肪を使うとありますが、痩せている人でもできますか?
A. 基本的には数mlの少量で治療に必要な幹細胞を得られますので、標準体型や痩せている方でも問題ないケースがほとんどです。
Q3. 幹細胞を採取する際の痛みやリスクはありますか?
A. 脂肪の採取は局所麻酔下で行うため、痛みは最小限に抑えられます。内出血や軽い腫れは起こる場合がありますが、大きなリスクは非常にまれです。
Q4. 治療効果はどのくらいで感じられますか?
A. 個人差がありますが、足潰瘍や神経障害などでは数週間から数か月で症状の改善を実感できる場合があります。腎症や網膜症は数か月から半年以上かけて徐々に改善が認められる傾向があります。
Q5. 保険適用はされますか?
A. 現在のところ、ADSC療法は自由診療(保険適用外)となっています。費用に関しては治療前にしっかりとご確認ください。
Q6. 一度採取した脂肪で何回治療ができますか?
A. 通常、一度の脂肪採取で複数回分の幹細胞を培養できます。3~6回程度の点滴が一般的で、再度脂肪を採取する必要はほぼありません。
Q7. 副作用はありますか?
A. 自分自身の細胞を使うため、拒絶反応などの重篤な副作用はほとんどありません。軽微な副作用として点滴後の一時的な発熱、注射部位の痛み・腫れなどがありますが、数日以内に改善します。
Q8. ADSC療法の効果はどのくらい持続しますか?
A. 症状や重症度にもよりますが、多くの臨床報告では治療後数年にわたり効果が維持される例もあります。定期的なフォローアップで効果を確認し、必要に応じて追加治療を行う場合があります。
Q9. どんなクリニックで治療を受けられますか?
A. 再生医療等安全性確保法に基づき厚生労働省の認可を受けた医療機関でのみ受けられます。信頼できる医療機関を選び、十分な説明を受けた上で治療を検討することをお勧めします。
自分の細胞で未来を切り拓く再生医療
糖尿病は一度発症すると長く付き合う病気ですが、ADSC療法のような再生医療はその風景を大きく変えるかもしれません。ここまで見てきたように、ADSC療法は糖尿病合併症の幅広い領域で有望な改善効果を示しています。
症状を和らげるだけでなく、傷んだ組織を修復・再生するという根本的なアプローチである点が革新的です。足潰瘍に対しては長期にわたり創面閉鎖を維持できたり、腎症に対しては進行を遅らせ透析導入を先延ばしにできる可能性が示唆されるなど、その効果の持続性にも希望が広がりました。さらに血糖コントロールの改善まで含めれば、患者さんの生活そのものを変えるポテンシャルを持っています。
糖尿病の合併症治療において、「もう治らない」「悪くなる一方」といった暗いイメージを払拭し、「自分の細胞の力で良くなるかもしれない」という希望を持てることは、患者さんの心の支えにもなります。医学は日進月歩です。自己脂肪幹細胞という “自分専用の名医” を味方につけて、これからの糖尿病医療はきっと今より明るい未来へと進んでいくことでしょう。
参考文献(エビデンスと出典)
1. Carstens MH, et al. (2021). Treatment of chronic diabetic foot ulcers with adipose‐derived stromal vascular fraction cell injections: Safety and evidence of efficacy at 1 year. Stem Cells Translational Medicine, 10(8), 1138-1147.
2. Liu X, et al. (2023). Safety and Preliminary Efficacy of Mesenchymal Stromal Cell (ORBCEL-M) Therapy in Diabetic Kidney Disease: A Randomized Clinical Trial (NEPHSTROM). J Am Soc Nephrol, 34(10), 1733-1746.
3. Packham DK, et al. (2016). Allogeneic Mesenchymal Precursor Cells (MPC) in Diabetic Nephropathy: A Randomized, Placebo-controlled, Dose Escalation Study. EBioMedicine, 12, 263-269.
4. Mikłosz A, Chabowski A. (2024). Efficacy of adipose-derived mesenchymal stem cell therapy in the treatment of chronic micro- and macrovascular complications of diabetes. Diabetes Obes Metab, 26(3), 793-808.
5. Yan D, et al. (2024). Progress and application of adipose-derived stem cells in the treatment of diabetes and its complications. Stem Cell Res Ther, 15(1), 3.
6. Rahimi-Movaghar V, et al. (2024). Human studies of the efficacy and safety of stem cells in the treatment of diabetic peripheral neuropathy: a systematic review and meta-analysis. Stem Cell Res Ther, 15(1), 442.
7. Jurowski P, et al. (2025). Future Directions in Diabetic Retinopathy Treatment: Stem Cell Therapy, Nanotechnology, and PPARα Modulation. Int J Mol Sci, 26(4), 1625.
8. Wu J, et al. (2022). Mesenchymal stem cell-derived exosomes: The dawn of diabetic wound healing. World J Diabetes, 13(12), 1066-1095.







とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)




