神経障害とは?
神経障害とは、脳・脊髄・末梢神経といった神経系のどこかに異常が生じ、神経の伝達がうまくいかなくなる病気の総称です。
症状は障害を受けた神経の場所によって異なりますが、代表的なものには次のようなものがあります。
- 手足のしびれやチクチクする感覚
- 感覚の鈍さ(温度や痛みを感じにくくなる)
- 焼けるような痛みや電気が走るような違和感
- 筋肉の力が入らない、動かしにくい
- バランス感覚の低下や歩行の不安定
特に手足の末梢神経は細くて長いため障害を受けやすく、しびれや痛みが続く「末梢神経障害」として現れることが多いです。
こうした神経の異常は一時的なものではなく、進行すると慢性的に続くことがあり、生活の質(QOL)を大きく低下させてしまいます。
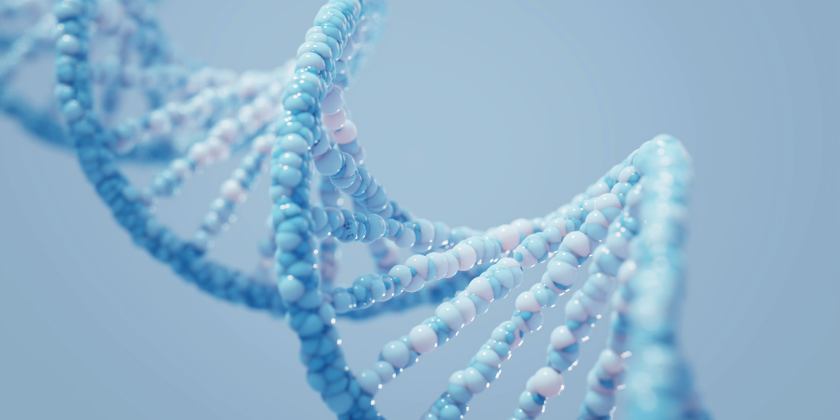
糖尿病・外傷・加齢など、神経障害を引き起こす主な原因
神経障害の原因はさまざまですが、最も多いのは 糖尿病性神経障害 です。高血糖状態が長く続くと、神経に栄養を届ける毛細血管が傷つき、酸素や栄養が不足して神経が徐々に壊れていきます。
そのほかにも次のような原因が挙げられます。
- 外傷や手術による神経の損傷
- ヘルニアや脊椎疾患による圧迫性障害
- 脳卒中や脊髄損傷による中枢神経のダメージ
- 加齢による神経の変性や血流低下
- 抗がん剤・アルコール・薬剤などによる毒性神経障害
一見、原因が異なるように見えますが、どのケースも最終的には「神経が損傷し、情報が正しく伝わらなくなる」という同じ仕組みで症状が現れます。
放置するとどうなる?神経障害が進行したときのリスク
神経障害を放置すると、症状が慢性化し、回復が難しくなるリスクが高まります。特に糖尿病性神経障害の場合、初期の軽いしびれを放置しているうちに、次のような合併症を引き起こすことがあります。
- 足の感覚が鈍くなり、傷や感染に気づかず悪化する(糖尿病性壊疽)
- 歩行困難や転倒のリスクが増加する
- 慢性の神経痛が続き、睡眠や活動に支障をきたす
- 重度の場合、麻痺や運動障害が残ることも
神経は一度損傷すると自然回復が非常に難しいため、「早期治療」が何よりも重要です。症状が軽いうちに治療を始めることで、神経の再生や機能回復の可能性を高めることができます。
従来の神経障害治療と限界
薬物療法(ビタミン剤・神経修復薬)の効果と課題
これまで神経障害の治療は、主に 薬による症状緩和 が中心でした。代表的なものとしては、ビタミンB12(メコバラミン)やビタミンB1誘導体などの「神経修復作用を持つビタミン剤」、また痛みを抑える「鎮痛薬」や「抗けいれん薬(プレガバリンなど)」があります。
これらの薬は、損傷した神経の代謝をサポートしたり、痛みの信号を遮断することで一時的な症状緩和が期待できます。
しかし、根本的に「壊れた神経を修復する力」は限られており、長期間の服用が必要になることが多いのが現状です。
また、鎮痛薬の中には副作用として眠気やふらつき、胃腸障害などが起こることもあり、患者さんの生活に新たな負担を生むこともあります。
神経ブロック注射やリハビリ治療の役割
神経ブロック注射は、局所麻酔薬を神経や神経の周囲に注射して痛みの伝達を遮断する方法です。
痛みの緩和には効果的ですが、効果は一時的であり、注射の回数を重ねなければならない場合も少なくありません。
一方、リハビリテーションは神経の伝達機能を刺激し、筋肉の硬直や関節拘縮を防ぐことを目的としています。
適切なリハビリを続けることで一定の改善が得られるケースもありますが、「神経自体を再生させる」わけではありません。
つまり、従来の治療は「神経のダメージを一時的に緩和する」ことには効果的でも、「損傷した神経を根本的に回復させる」ことは困難だったのです。
なぜ神経は一度損傷すると回復が難しいのか?
神経が再生しにくい最大の理由は、「神経細胞(ニューロン)」が成熟すると分裂能力をほとんど失ってしまうためです。
つまり、損傷を受けた神経細胞は自力で再生することがほとんどできません。
また、神経を包む「髄鞘(ずいしょう)」が壊れると、電気信号が正しく伝わらなくなり、再生のための環境そのものが悪化します。
さらに、損傷部位では炎症が長期間続くため、再生を阻害する因子(サイトカインなど)が増えてしまい、修復が進まなくなるのです。
その結果、従来の治療では「これ以上悪化させない」「痛みをコントロールする」という対症的なアプローチに留まらざるを得ませんでした。
しかし、近年の研究により、損傷した神経を細胞レベルで修復する可能性がある 幹細胞治療 が注目を集めています。
幹細胞治療が神経障害の新しい選択肢として注目される理由
幹細胞が神経再生を促すメカニズム
幹細胞は、自分自身を増やす「自己複製能力」と、さまざまな細胞に分化する「多分化能」を持っています。
これを利用して、損傷した神経の修復をサポートするのが再生医療(幹細胞治療)です。
投与された幹細胞は、神経細胞そのものに分化するわけではなく、周囲の環境を整えることで修復を促します。
具体的には、幹細胞が分泌する成長因子(NGF、BDNF、VEGFなど)が神経の生存を助け、損傷部位の炎症を抑えながら再生を促進します。
この「パラクリン効果」と呼ばれる働きによって、幹細胞は直接的な細胞置換よりも、「神経が自ら修復する力を引き出す」役割を果たすと考えられています。
炎症を抑制し、神経の修復を助ける作用
神経障害では、炎症が長期間持続することで神経のダメージがさらに悪化します。
幹細胞はこの炎症を抑える抗炎症性サイトカインを分泌し、同時に損傷部位の血流を改善する作用があります。
これにより、酸素と栄養が神経細胞へ届きやすくなり、細胞の回復を助ける環境が整います。
また、炎症が抑えられることで神経痛の軽減にもつながると考えられています。
このように幹細胞治療は、単に「神経を置き換える治療」ではなく、「神経が再生できる環境を再構築する治療」として注目されています。
「症状を抑える」から「神経を再生させる」治療へ
従来の神経障害治療は、「痛みを抑える」「しびれを軽減する」といった対症療法が中心でした。
しかし、幹細胞治療はこれまで難しいとされてきた「神経そのものの再生」を目指す新しいアプローチです。
幹細胞が持つ修復・再生能力を活かすことで、損傷した神経が再び機能を取り戻す可能性があるのです。
つまり、「症状を抑える治療」から「根本的に神経を再生させる治療」へ──。
この転換こそが、幹細胞治療が多くの専門医から注目される理由であり、神経障害治療における大きな希望となっています。
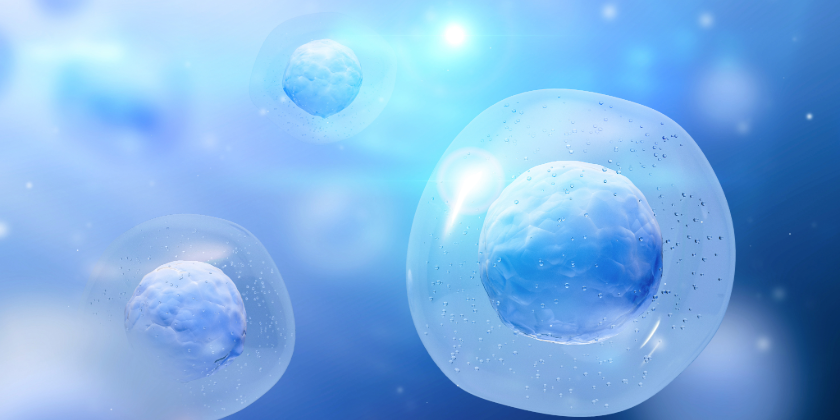
幹細胞治療で期待できる神経障害の改善効果
しびれ・痛みの軽減と感覚機能の回復
神経障害に伴う「しびれ」や「焼けるような痛み」は、患者さんにとって最もつらい症状のひとつです。従来の薬物療法では一時的に痛みを緩和できても、根本的な改善にはつながりにくいという課題がありました。
幹細胞治療では、損傷した神経の炎症を抑え、神経線維の修復を促すことで、痛みやしびれの軽減が期待されています。実際に臨床研究では、幹細胞投与後に末梢神経の伝導速度が改善し、患者さんが「しびれが弱まった」「痛みが減った」と感じる例も報告されています。
また、神経が回復すると感覚の伝達が正常化し、温度や触覚への反応が戻るケースもあります。これは、幹細胞が神経伝達物質のバランスを整え、神経回路の再形成を助けることによるものと考えられています。
末梢神経の修復による運動機能の改善
神経障害が進行すると、筋肉にうまく信号が伝わらなくなり、手足の動きが悪くなる、あるいは力が入らないといった運動障害が起こります。
幹細胞治療では、損傷した末梢神経の再生を促すことで、筋肉への信号伝達が改善され、運動機能の回復が期待されます。
研究では、幹細胞が神経細胞やシュワン細胞(神経を保護・支える細胞)の再生をサポートし、神経と筋肉の連携を回復させることが示唆されています。その結果、以下のような効果が報告されています。
- 歩行の安定性が向上する
- 手指の細かい動きがスムーズになる
- 筋力低下が改善し、日常動作が楽になる
これらの変化は、リハビリテーションとの併用によってさらに効果が高まると考えられています。幹細胞治療は「動ける体を取り戻す」ための基礎を作る治療ともいえるでしょう。
慢性神経痛や麻痺の進行を防ぐ可能性
長期間続く慢性神経痛や、麻痺などの重い神経障害は、日常生活だけでなく精神的にも大きなストレスとなります。幹細胞治療には、こうした慢性化した神経障害の進行を抑える 効果も期待されています。
幹細胞は損傷した神経周囲の炎症を鎮め、血流を改善しながら、神経細胞の酸素・栄養供給を助けます。これにより、神経のさらなる変性を防ぎ、残存する神経機能を保護する作用があると考えられています。
実際に、脊髄損傷や糖尿病性神経障害の研究では、幹細胞を投与することで神経伝導の低下を抑え、長期的に症状の悪化を防いだという報告もあります。
つまり幹細胞治療は、「失われた機能の回復」と同時に「残された機能を守る」治療でもあるのです。
神経障害の種類別に見る幹細胞治療の可能性
糖尿病性神経障害:手足のしびれや感覚低下への改善
神経障害の中でも特に患者数が多いのが「糖尿病性神経障害」です。高血糖状態が続くと、神経へ栄養を送る毛細血管が障害され、神経細胞への酸素や栄養が不足します。その結果、手足のしびれや痛み、温度感覚の鈍さなどが現れます。
幹細胞治療では、幹細胞が放出する 血管新生因子(VEGFなど) によって新しい血管が作られ、神経への血流が改善する可能性があります。また、炎症を抑えるサイトカインの分泌によって神経の炎症が鎮まり、しびれや痛みの軽減が期待されます。
さらに、損傷した末梢神経の再生を助ける「神経成長因子(NGF)」の産生が促されることで、感覚機能の回復が見込まれています。これにより、「足先の感覚が戻ってきた」「痛みが軽くなった」といった臨床報告も出てきています。
坐骨神経痛・腰椎疾患による神経障害への応用
坐骨神経痛や腰椎ヘルニアによる神経障害は、神経が物理的に圧迫されることで発症します。長期間続く圧迫は神経を損傷させ、慢性的な痛みやしびれを引き起こします。
幹細胞治療では、幹細胞が分泌する成長因子や抗炎症性サイトカインが、圧迫によって傷ついた神経組織の修復をサポートします。これにより、以下のような改善が期待されます。
- 坐骨神経の炎症が軽減し、痛みが和らぐ
- 神経伝達が改善し、下肢のしびれや脱力感が軽減する
- 椎間板周囲の炎症が抑えられ、神経の回復環境が整う
従来のブロック注射や手術では難しかった「神経の再生」という側面に働きかけられる点で、幹細胞治療は新しい選択肢として注目されています。
脳卒中後・脊髄損傷後の神経再生治療の研究状況
脳卒中や脊髄損傷のように「中枢神経」が損傷した場合、従来の医学では回復が極めて困難とされてきました。これは、中枢神経細胞が一度壊れると再生能力がほとんどないためです。
しかし、幹細胞治療の研究が進むにつれ、中枢神経でも再生を促す可能性 が示されています。幹細胞が神経栄養因子(BDNFやGDNFなど)を分泌し、損傷部位の神経細胞を保護すると同時に、新たな神経回路の形成を助けることが分かってきました。
臨床研究の段階では、幹細胞を脊髄や脳の周囲に投与した患者で、感覚や運動機能が一部回復したケースも報告されています。特に脊髄損傷では、「完全麻痺から部分的に手足が動くようになった」「感覚が戻り始めた」といった報告が注目を集めています。
まだ研究段階ではありますが、「神経は再生しない」という常識が覆りつつあるのは確かです。今後、幹細胞治療は脳卒中や脊髄損傷などの重度神経障害にも応用が広がっていくと期待されています。
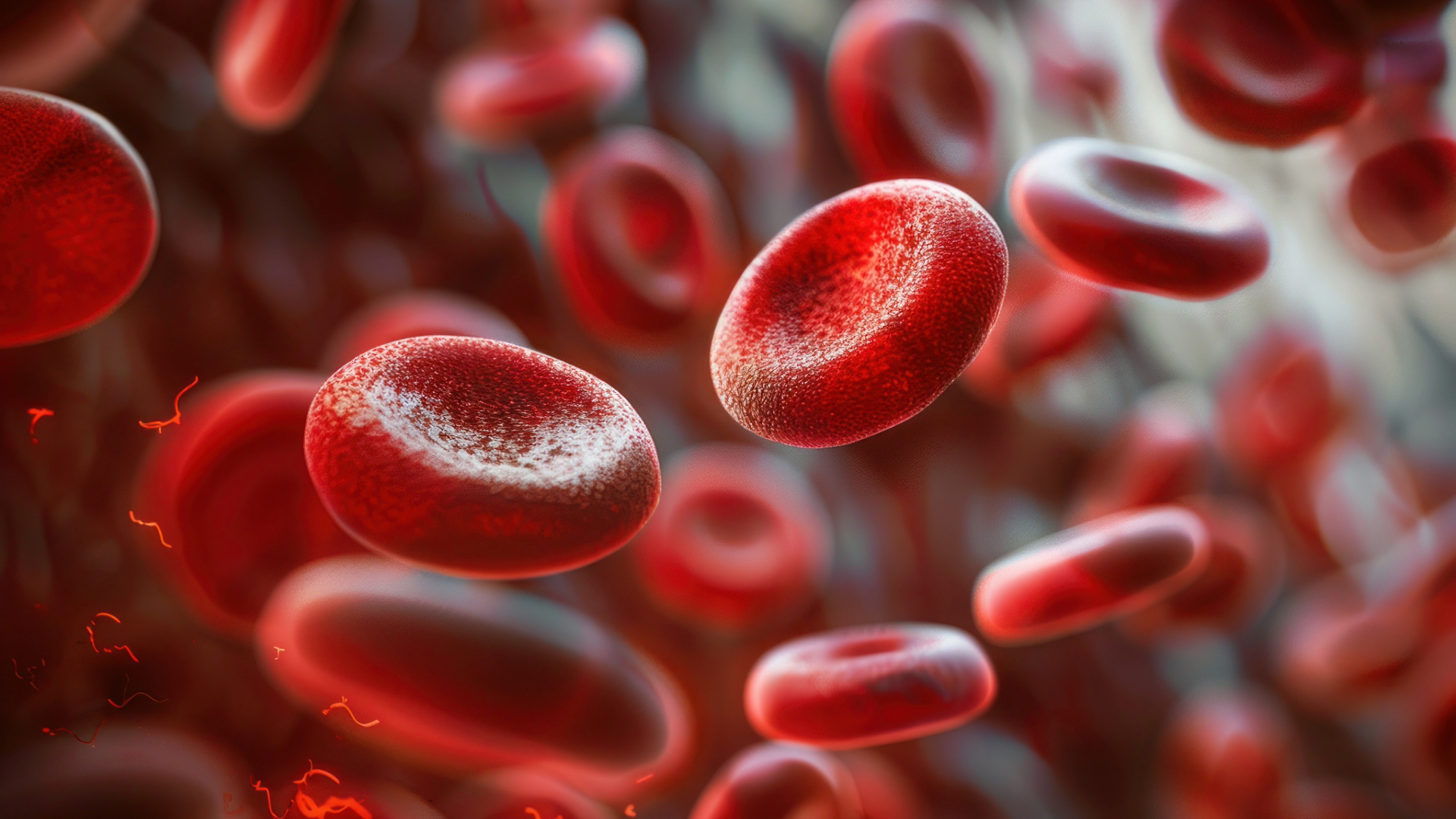
幹細胞の種類と神経障害への応用
脂肪由来幹細胞(ADSC)による神経修復の仕組み
神経障害の幹細胞治療で現在もっとも臨床応用が進んでいるのが、脂肪由来幹細胞(ADSC:Adipose-derived stem cells) です。患者さん自身の腹部や太ももなどから少量の脂肪を採取し、そこから幹細胞を分離・培養して使用します。
ADSCの特長は以下の3点です。
①採取が容易で負担が少ない
骨髄採取に比べて手技が簡単で、安全性が高い。
②細胞数が多く、増殖力が高い
少量の脂肪からでも豊富な幹細胞を確保できるため、治療までの期間を短縮できる。
③強い抗炎症・修復促進作用
ADSCは神経栄養因子(NGF、BDNFなど)を多く分泌し、損傷神経の再生を助ける。
これらの働きにより、ADSCは「神経そのものを再生させる可能性が高い幹細胞」として期待されています。
すでに糖尿病性神経障害や末梢神経損傷の臨床研究で、安全性と有効性が確認されつつあります。
神経細胞への分化誘導研究と臨床応用の現状
幹細胞が神経細胞に「分化」する(変化する)メカニズムについても研究が進んでいます。
実験では、幹細胞を特殊な培地で培養することで「ニューロン様細胞」への分化が確認されており、将来的には失われた神経そのものを作り出す治療が実現する可能性もあります。
現在、世界各国で神経損傷(脊髄損傷・脳梗塞・末梢神経切断など)に対する臨床試験が進行中です。
日本でも、脂肪由来幹細胞や骨髄幹細胞を用いた治療で、運動機能や感覚機能の改善が報告されています。
この分野は今まさに発展途上であり、幹細胞の分化制御技術や安全性が確立されれば、神経障害に対する再生医療は次のステージへと進むでしょう。
幹細胞治療による神経障害改善のメリット
薬のような副作用が少なく体への負担が軽い
幹細胞治療の大きな魅力は、「副作用が少ないこと」です。
患者さん自身の細胞(自家細胞)を使用する場合、拒絶反応やアレルギーの心配がほとんどなく、免疫抑制剤も必要ありません。
また、投与方法も点滴や局所注射が中心で、手術のような大きな負担はありません。
薬のように毎日服用する必要もないため、身体へのストレスが少ない治療といえます。
治療後は軽い発熱や倦怠感を感じることがありますが、ほとんどが一時的で自然におさまります。
慢性的な痛みやしびれからの解放が期待できる
神経障害は、痛みやしびれが長期間続く「慢性化」が大きな問題です。
幹細胞治療によって炎症が鎮まり、神経の伝達が改善されることで、痛みの信号そのものが減少します。
「薬を飲んでも痛みが取れなかった」「夜も眠れないほどの神経痛があった」といった方でも、治療後に痛みが軽くなり、睡眠や活動が改善したケースが報告されています。
さらに、症状が落ち着くことで精神的なストレスも軽減され、生活全体の満足度が上がるという効果も期待されています。
早期治療により神経の再生力を最大限に引き出す
神経は「損傷から時間が経つほど再生が難しくなる」組織です。
そのため、幹細胞治療は早期に行うほど高い効果が期待されます。
発症から時間が経ち、炎症や線維化が進むと、幹細胞が作用するための環境が悪化してしまうためです。
早い段階で治療を行えば、幹細胞が再生因子を放出しやすく、神経修復がよりスムーズに進みます。
「まだ軽いしびれだから」と放置せず、早めに専門医に相談することが、神経障害を根本から改善するための最良のステップとなります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 神経障害はどのように診断されるのですか?
A. 問診や神経学的検査に加え、神経伝導速度検査やMRIなどで障害の場所や程度を確認します。糖尿病性神経障害の場合は血糖コントロールの状態も重要な指標となります。
Q2. 神経障害は自然に治ることがありますか?
A. 軽度で一時的な圧迫などが原因の場合は自然回復することもありますが、多くの慢性神経障害では自然治癒は難しく、早期の治療介入が必要です。
Q3. 幹細胞治療はどんな神経障害に有効ですか?
A. 糖尿病性神経障害、外傷後や手術後の末梢神経損傷、坐骨神経痛、脊髄損傷後の神経障害などで臨床研究が進んでおり、特に炎症や虚血が関与するタイプで効果が期待されています。
Q4. 幹細胞はどのように投与されるのですか?
A. 点滴で全身に投与する方法と、しびれや痛みの強い部位の近くに局所注射する方法があります。症状の種類や範囲によって最適な投与法を選択します。
Q5. 治療効果はどのくらいで現れますか?
A. 早い方では数週間で痛みやしびれの軽減を感じるケースもありますが、多くは2〜3か月かけて徐々に改善が見られます。効果の持続や変化には個人差があります。
Q6. 幹細胞治療のリスクや副作用はありますか?
A. 自身の脂肪から採取した幹細胞を使う場合、拒絶反応のリスクはほとんどありません。副作用は一時的な発熱や倦怠感など軽度なものが主で、重篤な合併症は極めて稀です。
Q7. 幹細胞治療と薬やリハビリは併用できますか?
A. はい、併用可能です。幹細胞治療は神経の再生環境を整える治療であり、薬物療法や理学療法と併せて行うことでより高い効果が期待されます。
Q8. どのくらいの期間で再発を防げますか?
A. 幹細胞治療は根本的な神経修復を促すことを目的としており、再発予防にも有用と考えられています。ただし、生活習慣や基礎疾患(糖尿病など)の管理も重要です。
Q9. 幹細胞治療は高齢者でも受けられますか?
A. はい。全身状態が安定していれば高齢の方でも可能です。むしろ加齢による神経の再生力低下を補う目的で受けられるケースも増えています。
Q10. 幹細胞治療の費用と回数はどのくらいですか?
A. 保険適用外の自由診療のため、1回あたり数百万円程度が一般的です。症状や改善度に応じて1〜3回の投与を行うケースが多く、医師との相談で最適なプランを決めます。
幹細胞治療を検討する際に知っておきたいこと
どんな人が幹細胞治療に向いているのか?
幹細胞治療はすべての神経障害に適用されるわけではありません。
一般的に次のような方が適しています。
- 薬物療法やリハビリでも改善が乏しい慢性神経障害の方
- 糖尿病性神経障害など、血流や代謝の問題が関与する方
- 手術による神経修復が難しい方
- 全身状態が安定しており、重度の感染症やがんを合併していない方
また、早期に治療を始めることで回復率が高まることが分かっています。
治療の安全性・リスク・費用の実際
幹細胞治療は、これまでの臨床研究で高い安全性が確認されています。
副作用は一時的な発熱や倦怠感など軽度なものがほとんどで、深刻な合併症は極めて稀です。
幹細胞治療が拓く神経障害治療の未来
研究で明らかになりつつある神経再生のメカニズム
神経は「一度壊れると再生しない」と長く考えられてきました。
しかし、幹細胞が分泌する成長因子や神経栄養因子の研究が進むことで、神経組織の再生メカニズムが少しずつ明らかになってきています。
これまでの常識では考えられなかった「中枢神経の修復」や「神経伝達経路の再構築」も、実験レベルでは実現し始めています。
今後はAIやバイオ技術の進歩とともに、幹細胞の分化制御や移植効率がさらに向上し、治療成績が飛躍的に高まると期待されています。
今後、治療の主流となる可能性と課題
幹細胞治療は、薬やリハビリに代わる“次世代の標準治療”として注目されています。
今後さらに臨床データが蓄積され、安全性と有効性が確立されれば、神経障害治療の主流となる可能性があります。
一方で、課題も残っています。
- 細胞培養のコストと時間
- 治療効果の個人差
- 長期的なフォローアップデータの不足
こうした課題を解決するため、国内外で多くの研究が進められています。再生医療がより身近な治療法になる日は、確実に近づいています。
神経障害を「治らない病気」から「治せる病気」へ
幹細胞治療の登場によって、神経障害は「症状を抑えるだけの病気」から「根本的に回復を目指せる病気」へと変わりつつあります。
これまで諦めるしかなかった慢性的なしびれや痛み、麻痺に対しても、細胞レベルでの再生が現実味を帯びてきました。
もちろん、すべての症状が完全に治るわけではありません。
それでも、「改善の余地がある」「希望を持てる」という事実は、患者さんの生活や心に大きな光をもたらします。
当院では、こうした最先端の再生医療を通じて、一人ひとりの神経機能の回復と生活の質の向上をサポートしています。
諦めていた神経の痛みやしびれに、新しい選択肢としての再生医療を──。
未来の医療は、すでにここから始まっています。







とは?老化を招く体内の焦げつき-150x84.png)




